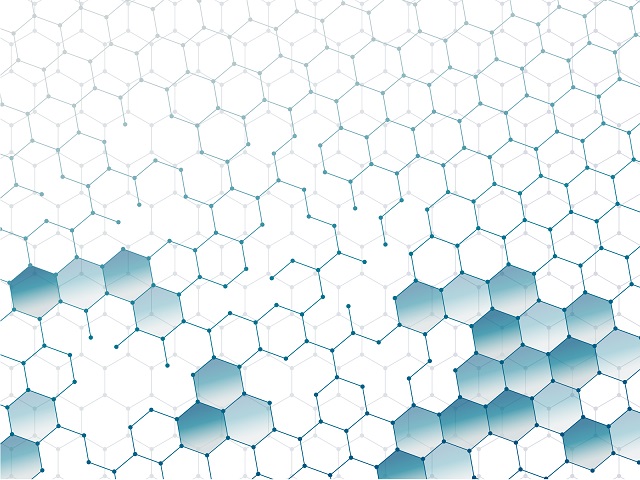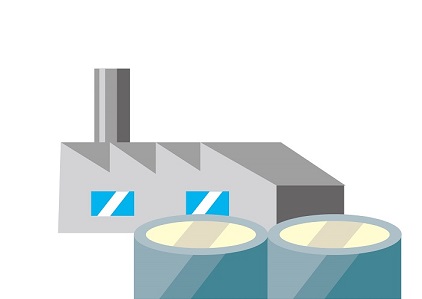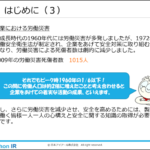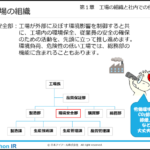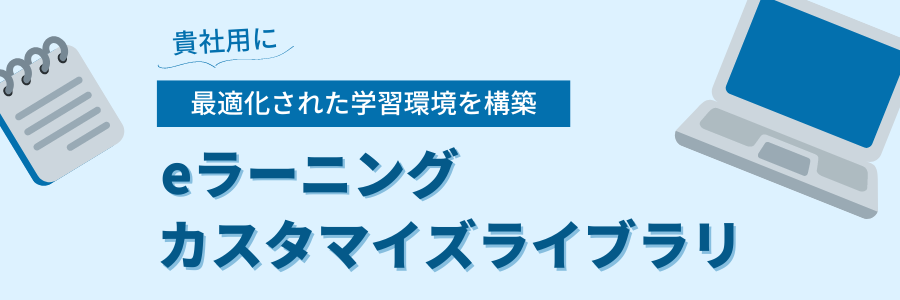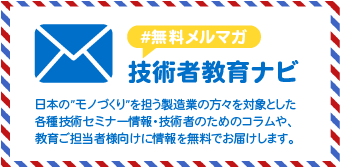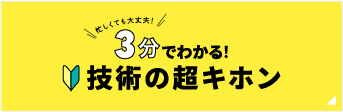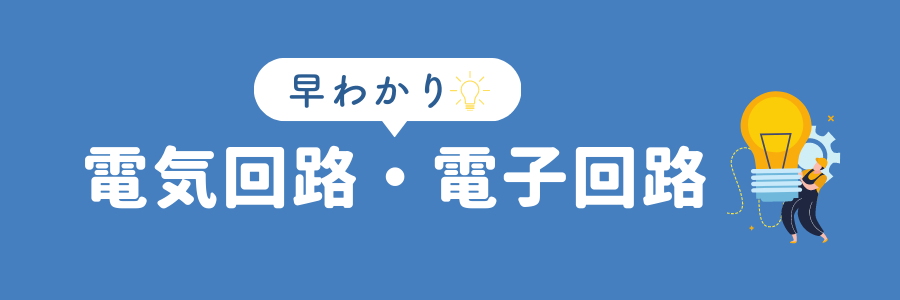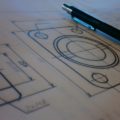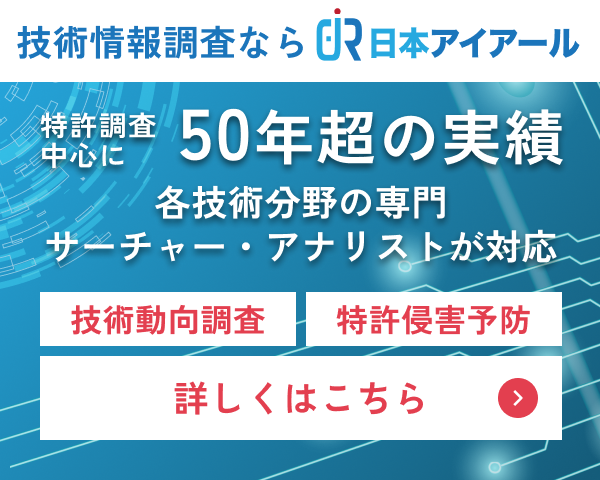消防法における「危険物」の種類と概要をわかりやすく整理|1類~6類の特徴と注意点

消防法では、火災の発生・拡大の危険性がある物質を「危険物」として定めています。
第一類から第六類まで分類されており、シンナーやガソリンなど第四類の物質は分かりやすいですが、意外なところでは鉄粉も危険物として定められています。また、単独では不燃物であるものの混合物では火災の恐れがある酸化性液体も危険物です。
こうした物質は工場の身近なところにあるため、工場の管理者や安全対策担当の方はもちろん、生産職に従事されている皆様に広く知っておいて頂きたいものです。
今回は消防法で定められている危険物について解説します。
目次
1.燃焼の3要素と消防法
(1)燃焼の3要素
危険物について解説する前に、そもそも火が起きる原因について見ていきましょう。
「火」とは燃焼反応に伴う光と熱を発する現象のことです。
燃焼反応は多数の素反応で構成されますが、簡略化すると次のような化学式で表すことができます。
基本的にはM、CH₄といった可燃物と酸素が共存するだけでは燃焼は起きず、燃焼反応の発生には「熱」も必要です。火の熱も延焼の原因となるほか、工場ではヒーターの熱、屋外では日光による放射熱も燃焼の原因となる場合があります。可燃物・酸素・熱は「燃焼の3要素」と呼ばれています。
M + O₂ → MO₂ (M:金属元素など)
CH₄ + O₂ → CO₂ + 2H₂O (メタンの例)
ちなみにガソリン等に含まれる炭化水素は燃焼(酸化)反応の構成要素となりますが、木材やプラスチックが燃える際には、原料となるリグニンやポリプロピレンが酸素と直接反応するわけではありません。
熱源に近づくことでリグニンや高分子の熱分解が起き、メタンなどの可燃性ガスを発生させ、これらが酸素と反応することで燃焼反応が進みます。
(2)消防法における危険物
消防法では次のような性質を持つ物質を危険物として定めています。
- 火災発生の危険性が大きいもの
- 火災拡大の危険性が大きいもの
- 消火の困難性が高いもの
それぞれの特徴ごとに第一類から第六類まで分類されており、燃焼時に水で消火しようとすると逆に延焼させてしまうものもあるため、扱う場合は各物質の特徴を覚えておく必要があります。
次項では各類の代表的な成分と特徴について解説します。
2.第一類~第六類物質の特徴
(1)第一類 酸化性固体
塩素酸カリウム(KClO₃)や過マンガン酸カリウム(KMnO₄)といった塩素酸塩類や無機過酸化物などは、酸化性固体として危険物に定められています。
分子中に酸素原子を含んでおり、これ以上酸化しないため第一類物質自体は燃焼しません。しかし、可燃物と第一類成分の混合物は熱や衝撃、摩擦によって燃焼を引き起こす危険性があります。
これは第一類物質に含まれる酸素が可燃物に供給し、酸化(燃焼)反応を引き起こすためです。
なお、基本的に消防法では異なる類の物質同士を同時に貯蔵することはできず、相互に1m以上分離させるなどの対策を取る必要があります。
(2)第二類 可燃性固体
第二類物質は、火炎によって着火しやすい固体又は比較的低温(40度未満)で引火しやすい固体です。
赤リンや硫黄などの無機物、鉄粉や亜鉛末などの金属粉は第二類物質に定められています。
出火しやすく燃焼が速いため、消火が困難という特徴があります。鉄板などの金属素材は燃えにくい印象がありますが、粉末状では酸素と接する表面積が広がるため燃焼の危険性も高まります。
なお、同じ第二類の物質であっても火災発生時の対処法は異なります。
赤リンは水による消火が有効ですが、硫化リン物質や金属粉の場合は注水厳禁です。
アルミニウム粉は下式のように水と反応し可燃性ガスの水素を発生させてしまいます。
2Al + 6H₂O → 2Al(OH)₃ + 3H₂
禁水の物質が燃えている際は、乾燥砂などをかけて窒息消火させるようにしましょう。
(3)自然発火性物質及び禁水性物質
第三類物質は「空気にさらされることにより自然に発火する危険性を有し、又は水と接触して発火し若しくは可燃性ガスを発生するもの。」と定義されています。
具体的にはカリウム、ナトリウム、アルキルリチウム、水素化ナトリウムなど、アルカリ金属やアルカリ土類金属の化合物がこれにあたります。
水と反応して発火するものや、水素を発生するもの、空気中の湿気で自然発火するものなどがあり、こうした物質では禁水を厳守しなければなりません。一方で、黄リンの場合は空気中で自然発火してしまうため、水中に沈めて保存します。
第三類物質は特に保管状況に気を付けなければならない物質です。
火災発生時の対処法については、第三類の多くの物質が注水厳禁です。水が含まれるため泡消火器も使うことはできません。カリウムやリチウムについては、反応してしまうためハロゲン消火器の使用も不可です。
第三類物質を取り扱う場合は、乾燥砂や専用の消火器を常備しておく必要があります。
(4)第四類 引火性液体
第四類物質は最も身近な危険物で、ガソリンや灯油などの燃料、トルエンやヘキサンなどの溶媒類がこれにあたります。第四類は引火点や発火点によってさらに細かく分類されています。

「引火点」は、火を近づけたときに燃焼が始まる液体の温度のことです。
上記の表では上に行くほど引火点が低くなり、危険性が高くなります。第一石油類のガソリンは引火点がマイナス40℃以下であるため、室温でも火を近づけただけで燃焼が起きます。
第四類物質に由来する火災が起きてしまった場合は泡消火器、ハロゲン消火器、二酸化炭素による消火が有効です。トルエンのように水と混ざらない物質については注水をせず、水はあくまでも延焼防止や冷却用に用います。家庭での天ぷら油による火災でよく見られますが、水と混ざらない液体に注水するとむしろ火を広げてしまう可能性があります。
第四類物質は燃料、溶媒として工場でよく用いられている物質です。
少なくとも取り扱っている物質については性質を抑えておきましょう。
《指定数量について》
貯蔵量の制限を設けるため、危険物には「指定数量」が定められています。
危険性が高いほど指定数量は低く設定されており、第四類物質では分類ごとに数値が異なります。
第一石油類の指定数量は非水溶性液体で200L、水溶性液体で400Lです。第四石油類は6,000Lにもなります。
指定数量の1倍以上危険物を貯蔵する場合は消防法の規制を受け、貯蔵・取扱いの際に基準を守らなければなりません。
(5)第五類 自己反応性物質
第五類物質は「固体又は液体であって、加熱分解などにより、比較的低い温度で多量の熱を発生し、又は爆発的に反応が進行するもの。」と定められています。
MEKPOなどの有機過酸化物やニトロセルロースなどの硝酸エステル類、ニトロ化合物などが含まれます。
加熱・摩擦によって発火、爆発するほか、高温で分解する性質を有しており、触媒や重合開始剤、爆薬の原料として使われています。酸素を含みながらも不燃性である第一類物質に対し、第五類物質は酸素を含みつつ自身が可燃性であるものが多いため非常に危険性の高い物質です。一旦燃焼が始まると爆発的に燃焼が進んでしまいます。消火は困難で、鎮火までに大量の水を投入する必要があります(※加熱でナトリウムを生じるアジ化ナトリウムは禁水)。
ちなみにトリニトロトルエンによる燃焼・爆発の場合は自身が酸素を有しているため砂などによる窒息鎮火は無効です。
(6)第六類 酸化性液体
第六類物質は可燃性ではないものの、可燃性物質と混在させた場合、その燃焼を促進する性質があります。
保管の際は有機物や炭化水素(第四類物質)への混入を防止しなければなりません。第一類物質の液体バージョンと考えてよいでしょう。
過塩素酸(HClO₄)や過酸化水素(H₂O₂)、硝酸(HNO₃)、三フッ化臭素(BrF₃)などが該当します。
三フッ化臭素などのハロゲン間化合物は酸素供給源ではありませんが、酸化力が非常に強く、有機化合物と反応します。第六類物質との混合物が燃えてしまった場合、消火手段は可燃物によって適切なものを選択する必要があります。ただしハロゲン間化合物は水と激しく反応するため、同物質を含む場合は水による消火は不適切です。砂などを用いて窒息消火させる必要があります。
3.まとめ
以上、消防法で定められている危険物の特徴を解説しました。
各類・物質ごとに適切な保管条件や、燃焼時の対応が異なるため、複数の危険物を取り扱っている場合は各成分の特徴を覚えておく必要があります。
なお、第一類から第六類の危険物を全て取り扱うには「危険物取扱者 甲種」の資格を取得する必要があります(乙種は各類のみ)。
火災の危険性に関する知識を深めたい方は、資格取得を目指してみるのも良いでしょう。
(アイアール技術者教育研究所 G・Y)
《引用文献、参考文献》
- 1) 甲種危険物取扱者合格教本 (この1冊で決める! !),新星出版社(2015)
- 2) Safety & Tomorrow,No135,59-64(2011)
- 3) 総務省消防庁 (Webサイト)
https://www.fdma.go.jp/laws/laws/laws003.html