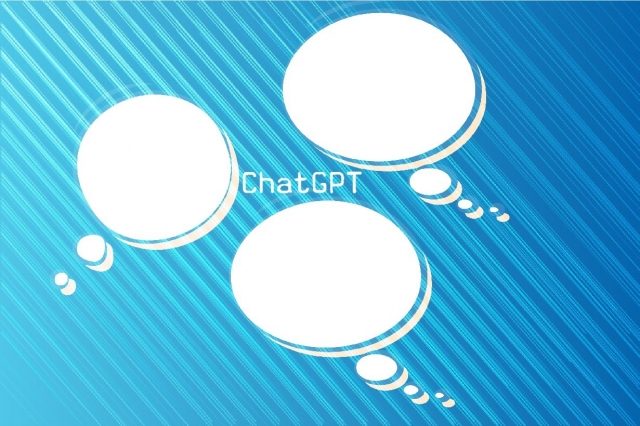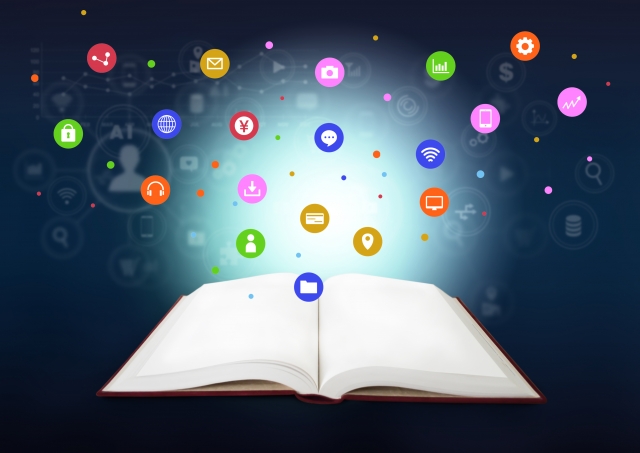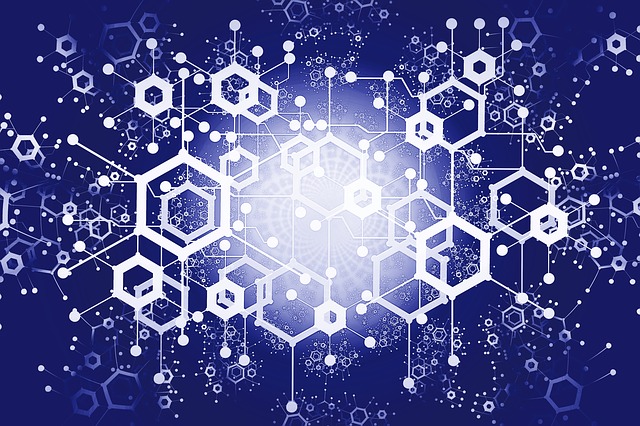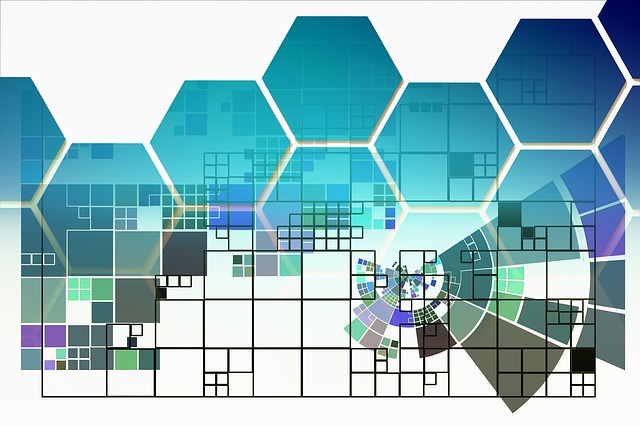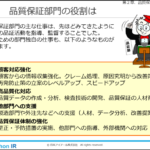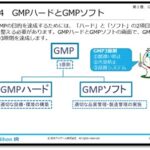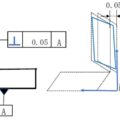改正GMP省令の重要ポイントを解説!データインテグリティなどの概要がわかる

2021年8月1にGMP省令の一部が改正され施行されました。
この記事ではGMP初心者の方に向けて改正点をわかりやすく解説します。特に、医薬品品質システムの導入、データインテグリティ概念の導入、OOS処理の明確化の3点を中心にご説明します。
[※GMP初心者向けの関連記事:GMPって何?|GMPの3原則など必須前提知識をチェック! はこちら]
目次
1.GMP省令の主な改正事項
まず改正GMP省令の全体像について、ご紹介します。
主な改正ポイントは、下記の14点です。製造部門、QC、QA、マネジメントにまで広く関わる改正になっています*1)。
- 承認事項の尊厳に関わる条文の新設
- 医薬品品質システムの導入
- 品質リスクマネジメントの省令化
- QA部門の設置の義務化
- データインテグリティ概念の導入
- 交叉汚染防止管理の新設
- 構造設備の共用等の管理の明確化
- 参考品、保存品管理の省令化
- OOS処理の明確化
- 安定性モニタリングの省令化
- 製品品質の照査の省令化
- 原料等の供給者管理の省令化
- 外部委託業者の管理の新設
- 変更マネジメント概念の導入
- 逸脱管理の強化
今回の改正は、国際整合性をより高める内容になりました。新設された条文が多いのも特徴です。この改正により、国際的にも通用する製造管理及び品質管理ができ、製品の輸出もスムーズになることでしょう。
改正された点のうち、関心の高いポイントや重要な考え方について、厳選して解説します。
2.医薬品品質システムの導入について
第3条の3医薬品品質システムは、新設された省令の一つです。
品質システムを統括する概念の設定と、定期的なマネジメントレビューが求められています。
具体的には次のとおりです。
- 品質方針を文書により定める
- 品質方針に基づいた製造所における品質目標を定める
- 品質方針及び品質目標を組織及び職員に周知する
- 定期的に医薬品品質システムを照査する(マネジメントレビュー)
複数の製造所を持つ会社の場合、品質方針は社内で1つ、工場ごとに品質目標を設定するのも可能です。
品質方針は、ICH-Q10の「1.8 品質マニュアル」*2) に相当します。
169 1.8 品質マニュアル
170 品質マニュアル又は同等の文書化された取り組みが確立され、その中には医薬品品質シス
171 テムの記述を含まなければならない。それらの記述には以下のことを含まなければならな
172 い:
173 (a) 品質方針(第2章参照);
174 (b) 医薬品品質システムの適用範囲;
175 (c) 医薬品品質システムのプロセス並びにそれらの順序、関連性及び相互依存性の特定。
176 プロセスマップ及びフローチャートは、医薬品品質システムのプロセスの視覚的な
177 説明を容易にする有効なツールとなり得る;
178 (d) 医薬品品質システムの中での経営陣の責任。(第2章参照)
179
品質方針はあるべき姿などを抽象的に表したものに対して、品質目標は具体的な数値として計測可能なものです。品質目標の具体例として、逸脱件数◯件以下、不良率◯%以下などがあります。
マネジメントレビューは、医薬品品質システムが継続的に保たれるよう、確認するために必要です。
会議では、現状のインプットと改善や改訂などのアウトプットを行います。
3.データインテグリティ概念の導入について
「データインテグリティ」(Data Integrity)とは、「文書及び記録の完全性」という概念で、GMPの基本で新たに考案されたものではありません。
しかし電子データが多く取り入れられている昨今、
- そのデータが正しく採取され
- 改変されないこと
- 修正した場合はその修正が妥当であること
- 責任の所在が明らかであること
- 正しい記録が維持されていること
- 記録が正しく再現可能であること
が強く求められています。
特に導入が多いExcelやスプレッドシートについて、書き換えが容易であることからデータインテグリティ担保の観点より、コンピューターシステムバリデーション(CSV)についての関心が高まっています。
そのためCSVの必要性と関連する指摘事項について、詳しく紹介します。
(1)コンピューターシステムバリデーション(CSV)の必要性
GMP省令の改正により、Excelやスプレッドシートなどのデータは、「医薬品・医薬部外品製造販売業者等におけるコンピュータ化システム適正管理ガイドラインについて 」*3)(薬食監麻発1021第11号平成22年10月21日)に従ってバリデーションの実施が求められました。
データ処理ソフトは、使いやすいツールとして普及していますが、以下のような可能性があるためコンピューターシステムバリデーション(CSV)が必要とされています。
- 手動入力による誤り
- 計算式の誤りや改ざん
- データの追跡不可能性
- 不適切なアクセスによるデータの書き換え
規制の準拠だけでなく、企業の信頼性強化、品質管理の向上、リスク管理の視点でもCSVは重要です。
CSVにより、製品の品質向上及び安全性の確保につながります。
[※CSVに関するセミナー情報はこちら]
(2)データインテグリティに関する指摘事項の実例
データインテグリティについての指摘事項の一例を紹介します*1)。
- 共有サーバーに保管された製造指図記録書の原本ファイルは上書き制限がかけられておらず、内容を書き換えることのできる状況であった。
- HPLCシステムの監査証跡において、データ削除を示唆するログが残っていたことを調査で認めたが、それらのデータが削除された理由及び妥当性が確認できなかった。
(その後の社内調査の結果、不適切なデータ削除、複数回分析・解析、時刻の操作等、不適切な取り扱いが多数の品目で判明) - HPLCの試験データの取り扱いやコンピュータシステムへのアクセス制限について、不備を認めた。
あなたの現場でもこれらの事例がないかどうか、確認してみましょう。
[※データインテグリティに関するセミナー情報はこちら]
4.OOS処理の明確化
「OOS」(Out of Specification)とは、「規格外試験結果」のことです。
改正GMP省令第11条において、「規格に適合しない結果となった場合においては、その原因を究明し、所要の是正措置及び予防措置をとるとともに、その記録を作成し、これを保管すること」と明記されました。
そのためOOSとなった場合は、まず試験手技によるものかどうかを判断し、そうでなければ製造作業に起因するものかどうかを見極めます。正しい処理を踏んだのち、OOS確定となるのです。
正しい処理を行わない場合、指摘の対象になります。
たとえば、初回試験が不適合になった場合、原因調査することなく追加試験を実施し、再試験ではなく初回試験と位置づけていたとして指摘を受けている事例がありました。また、試験手技で不具合があったが、再発防止策が取られていないということで、指摘されたこともあります。
職員は試験の失敗を公表したくない気持ちから、手順を踏まずに再試験してしまいたい、という心理になりがちです。しかしそれはGMP管理下において許されません。
そのため、職員に対する日々の教育は極めて重要といえるでしょう。
[※OOSに関するセミナー情報はこちら]
(アイアール技術者教育研究所 S・O)
《参考文献・サイト》
- *1) 嘉藤裕樹.改正GMP省令について-最近の指導事例を中心に.2022-09-09.p1-p44.独立行政法人医薬品医療機器総合機構,(2024).
https://www.jpma.or.jp/information/quality/jirei/gbkspa00000017ws-att/2022_1.pdf - *2) 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長.医薬品品質システムに関するガイドラインについて.平成22年,薬食審査発 0219 第1号,p5.PMDA,(2024).
https://www.pmda.go.jp/files/000156141.pdf - *3) 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長.医薬品・医薬部外品製造販売業者等におけるコンピュータ化システム適正管理ガイドラインについて.平成22年,薬食監麻発1021第11号.厚生労働省,(2024).
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb6573&dataType=1&pageNo=1