【医薬品製剤入門】徐放錠の基礎知識[種類/製法など]

「徐放錠」は、薬が長時間に渡って溶けだすように工夫された錠剤です。
薬の名前に、「L錠」とか「R錠」などがついていたりします。
効果が長く続き、薬を飲む回数を減らしたり、副作用を軽くしたりすることができるという利点があります。
今回は、徐放錠についてまとめてみました。
目次
1.徐放錠とは
日本薬局方では、[3] 製剤各条に「徐放性製剤」として、次のように記載されています。
「1.経口投与する製剤
(2) 経口投与する放出調節製剤は,固有の製剤設計及び製法により放出性を目的に合わせて調節した製剤で,腸溶性製剤,徐放性製剤などが含まれる.
(ⅱ)徐放性製剤
徐放性製剤は,投与回数の減少又は副作用の低減を図るなどの目的で,製剤からの有効成分の放出速度,放出時間,放出部位を調節した製剤である.本剤を製するには,通例,適切な徐放化剤を用いる.
1.1錠剤
(2) 本剤を製するには,・・・・適切な方法により,・・徐放錠とすることができる.
1.2. カプセル剤
(2) 本剤を製するには・・適切な方法により・・徐放性カプセル剤とすることができる
1.3. 顆粒剤
(2) 本剤を製するには・・適切な方法により,徐放性顆粒剤・・とすることができる」
通常、製剤の投与後には、血中濃度が急激に立ち上がり、その後低下していきます。
それに対し徐放性製剤の場合は、投与後の血中薬物濃度の急激な立ち上がりが少なく、長時間にわたり有効域内に維持される特徴があります。
ちなみに、徐放錠には、医薬品名の後にアルファベットが付くことがあります。
L錠、R錠、CR錠、SR錠など、いずれも徐放に関連した名称が由来となっています。
- L、LA = Long Acting (長時間効果)
- R = Retard (遅らせる)
- CR = Controlled Release (放出制御)
- SR = Sustained Release (持続的放出)
- TR = Time Release (持続放出)
2.徐放錠の特徴(メリット・デメリット)
徐放錠は、下記のようなメリットがある製剤です。
- 薬の効く時間をより長く持続させることができ、薬を飲む回数を減らすことができる。(患者のコンプライアンス向上)
- 投与後の血中薬物濃度について、急激な立ち上がりが少なく、副作用を軽くできる。 など
具体的には、アダラートL、CR錠(血圧降下薬)では、徐放錠とすることで服用回数を減らすことができた(1日2回を1日1回)とされています。ムコソルバンL錠やレキップCR錠についても同様に、1日3回を1日1回にすることが可能になりました。また、デパケンR錠は、他の抗てんかん薬と比較して半減期が短いものを徐放錠とすることで、臨床現場のニーズに応えることができたとされています。
特に、消失半減期の短い薬物では、徐放製剤にすることにより少ない投与回数で有効血中濃度を維持することができるようになります。
ただし、徐放錠には下記のようなデメリットもあります。
- 薬を長時間徐々に放出する設計になっているため1錠中の含有成分量が多く、噛んだり砕いたりすると、薬が急に放出されて薬の濃度が短時間で高くなり(過量放出)、重篤な副作用発現の危険性がある。など
なお、体内で薬が崩壊せずに、薬の形がそのまま便に排出されることがあり、これは「ゴーストピル」(ゴーストタブレット)といわれており、重度の下剤などでない限り、薬の主成分はほぼ吸収されているとされています。このゴーストピル(ゴーストタブレット)は徐放製剤で多く報告されており、製剤構造によるものと考えられます。
3.徐放錠(製剤)の種類
(1)形態上の種類
徐放錠(製剤)には、錠(投与形態)が消化管までその形状を保ったまま移行し、そこで徐々に薬物を放出する製剤(シングルユニット型)と、投与された錠(投与形態)がすぐに崩壊、顆粒となり、この顆粒が徐々に薬物を放出する製剤(マルチプルユニット型)があります。
① シングルユニット型
- ワックスマトリックス型錠剤:基剤(脂肪やろうなど)に薬物を分散させた錠剤で、基剤の崩壊により薬物が徐々に放出されます。ヘルベッサー錠、リスモダンR錠、デパケンR錠などがあります。
- グラデュメット型錠剤:多孔性プラスチックの網目構造の中に薬物が分散している錠剤で、浄化液が網目に侵入すると拡散により徐々に薬物が放出されます。
- レペタブ型錠剤:腸溶性コーティングを施した内核錠に速放性の外層を組み合わせたもので、胃で外層、腸で内核錠が溶けることにより薬効が持続する。ポララミン復効錠がこのタイプでした。
- ロンタブ型錠剤:徐放性マトリックス錠を速溶性外層で覆った有核錠剤です。アダラートCR錠が挙げられます。
- スパンタブ型錠剤:速溶層と徐放層からなる2層錠です。
② マルチプルユニット型
- スパスタブ型錠剤:徐放性コーティング顆粒を速溶性マトリックスに分散させた錠剤で、速溶性マトリックスが消化管内で溶解した後に顆粒から徐々に薬物が放出されます。テオドール錠、フランドル錠があります。
- スパンスル型製剤:薬物を含有する顆粒を高分子コーティングし、カプセルに充填した製剤です。コーティングの厚さが異なる顆粒を混合することで放出速度を調整します。たとえば、胃溶性顆粒と腸溶性顆粒の混合(顆粒型製剤)、速溶性と徐放性の組み合わせなどがあります。ペルジピンLAカプセル、L-ケフラール顆粒などがあります。
なお、錠剤以外として下記のものもあります。
(2)放出機構上の種類
薬物を含有する錠剤または顆粒を高分子皮膜でコーティングした「リザーバー型」と、薬物を高分子やワックスなどの基剤中に分散させた「マトリックス型」に分けられます。
① リザーバー型
レペタブ型、スパスタブ型、スパンスル型、顆粒型があり、薬物の放出速度はこの皮膜の性質や厚さで決まります。
② マトリックス型
ワックスマトリックス型、グラデュメット型、ロンタブ型、スパンタブ型などがあり、薬物分子のマトリックス内の拡散速度により放出速度は決まります。
4.徐放錠の製造方法
徐放錠の製法として、日本薬局方には、上記のように「適切な方法により・・徐放錠とすることができる.」とあります。
徐放製剤には種々の製剤があり、それぞれ製法が工夫されていますが、ここではマトリックス型製剤についてざっと取り上げてみます。
ワックスマトリックス型錠剤は、医薬とワックスとを溶融し、その後冷却することによる溶融法が一般的ですが、溶媒法や溶媒-溶融法によっても製造することができます。
また、流動層造粒機又は転動造粒機等を用いて、融点以上に加熱溶融したワックスを医薬結晶もしくは医薬を含んだ粉体混合末又はその造粒品に吹きつけることによって、またはワックスと粉体(医薬結晶及び粉体賦形剤)の溶融混合物を冷気中にスプレーすることによって、ワックスマトリックスを製造する方法なども知られています。
密度の高い被覆物を調製できるなど多くの利点があり、製造コストや環境に与える影響などの面でも、通常のコーティング技術に比べ有用性は高いとされています。
5.徐放錠の基剤・添加物
徐放錠に用いられる基剤・添加物は、その種類によって異なります。
ここでも一例として、マトリックス型製剤についてご紹介します。
マトリックス型製剤の放出制御基剤としては、親水性高分子を用いたハイドロゲル基剤やヒドロキシプロピルメチルセルロース(HPMC)、エチルセルロースやアクリル酸系の疎水性高分子、硬化ひまし油、硬化ダイズ油等の硬化油、グリセリン脂肪酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル類等、高級脂肪酸、高級アルコールなどのワックス類を用いることが知られています。一般的にはワックスの配合量は医薬品に対して重量比0.5~5倍程度が好ましいとされます。
6.徐放錠の試験法
日本薬局方では、医薬品として製造された徐放錠は通常の錠剤と同じように、下記試験法に適合することが定められています。
(1)製剤均一性試験法
個々の製剤間での有効成分量の均一性の程度を示すための試験法です。有効成分の含量が、表示量の一定範囲内にあることを確認し、均一性を保証します。製剤含量の均一性は、含量均一性試験又は質量偏差試験のいずれかの方法で試験されることになっています。第十七改正日本薬局方6.02に詳細な試験法が記載されています。
(2)溶出試験法
経口製剤について溶出試験規格に適合しているかどうかを判定するために、また、著しい生物学的非同等を防ぐことを目的としている試験です。腸溶性製剤、即放性製剤、徐放性製剤などによって試験方法、判定法が定められています。第十七改正日本薬局方6.10に詳細な試験法が記載されています。
(3)崩壊試験法
徐放錠が試験液中、定められた条件で規定時間内に崩壊するかどうか否かを確認する試験法です。製造工程のバラツキが小さいことを確認するための品質管理が主目的としています。第十七改正日本薬局方6.09に詳細な試験法が記載されています。
7.徐放錠の医薬品
添付文書情報で、徐放錠を調べてみると、以下のようになりました。
- 種類 : 徐放錠
- 医薬品数(*) :86以上
- 主な医薬品 : 「モルヒネ硫酸塩水和物徐放錠」「アンブロキソール塩酸塩徐放性口腔内崩壊錠」「オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠」「ジソピラミドリン酸塩徐放錠」「テオフィリン徐放錠」「ニフェジピンCR錠」「プラミペキソール塩酸塩LA錠」「ベザフィブラートSR錠」等々
(*)医薬品数はジェネリック医薬品なども含みます。
なお、カプセルや顆粒等の錠剤以外も含めると医薬品数は、134以上になります。
8.徐放錠に関する特許・文献調査
(1)徐放錠に関する特許検索
J-Platpatを用いて徐放錠の特許を調査してみました。(調査日:2022.7.12)
① キーワードによる検索
- 徐放錠/CL ⇒ 55件
- 徐放錠/CL+徐放/CL*錠/CL ⇒ 1180件
② 特許分類(IPC)による検索
徐放錠の特許を見てみると、A61K9/22[・丸剤または錠剤 ・・持続または徐放型のもの]が多く付与されているようですので、これを用いて検索してみます。
- A61K9/22/IP ⇒ 4210件
- A61K9/22/IP*(徐放錠/CL+徐放/CL*錠/CL) ⇒ 484件
これらの中には、「良好な徐放性を有する、レボドパ含有小型化錠剤」「含プレガバリン高膨潤性徐放性三重錠剤」「溶出率向上と副作用発現が最小化されたシルロスタゾール徐放錠」「徐放性塩酸アンブロキソール口腔内崩壊錠」等々の特許が見受けられました。
② Fタームによる検索
徐放錠に対応するFタームとしては4C076AA38[医薬品製剤 形態 ・丸剤;菱形剤;錠剤;トローチ剤;バッカル剤 ・・持続,徐放型]がありますので、これを用いて検索してみます。
- 4C076AA38/FT ⇒ 3206件
- 4C076AA38/FT*(徐放錠/CL+徐放/CL*錠/CL) ⇒ 461件
この中には、IPCでヒットしたものと同様な特許がヒットしていました。
(2)徐放錠に関する文献調査
J-STAGEを用いて文献調査を行ってみました。(調査日: 2022.7.12)
- 全文検索: 徐放錠 ⇒ 987件
- 抄録検索: 徐放錠 ⇒ 40件
- 全文検索: 徐放錠 or 徐放*錠 ⇒ 1686件
- 抄録検索: 徐放錠 or 徐放*錠 ⇒ 50件
「経口ベラプロストナトリウム徐放性製剤(ケアロード®LA錠60μg,ベラサス®LA錠60μg)の特徴および臨床試験成績」「テオフィリン徐放錠の溶出試験による品質評価」「新規統合失調症治療薬パリペリドンER(インヴェガ®錠)の薬理学的特性および臨床試験成績」などの文献が見られました。
これらの文献の内容を確認したい方は、ぜひ各データベースを検索してみましょう。
ということで今回は、「徐放錠」に関する基礎知識をご紹介しました。
(日本アイアール株式会社 特許調査部 S・T)



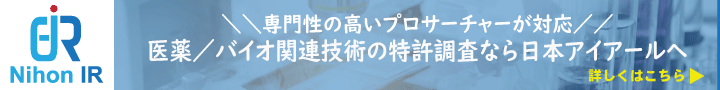





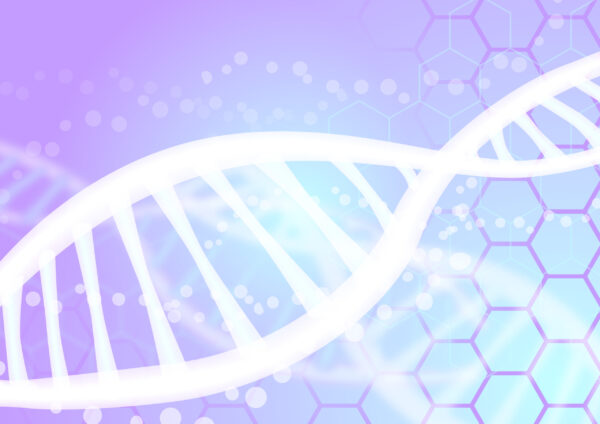
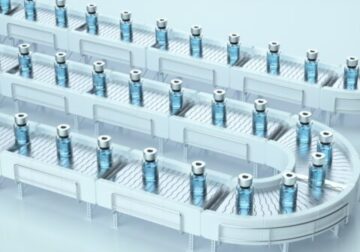


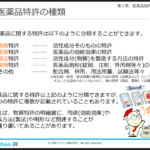
](https://engineer-education.com/wp/wp-content/uploads/2024/01/solubilizer-150x150.png)
































