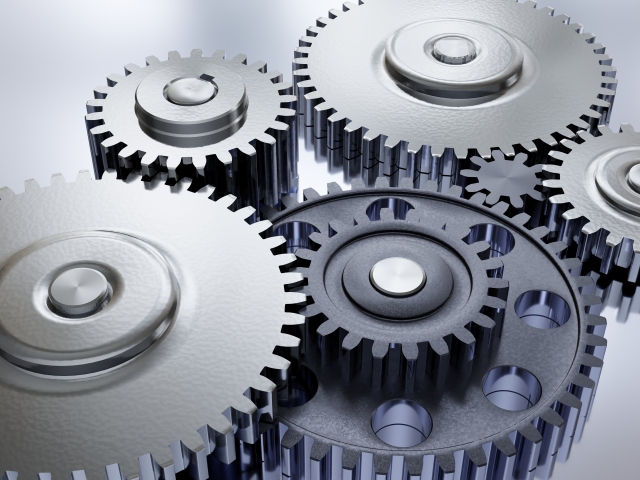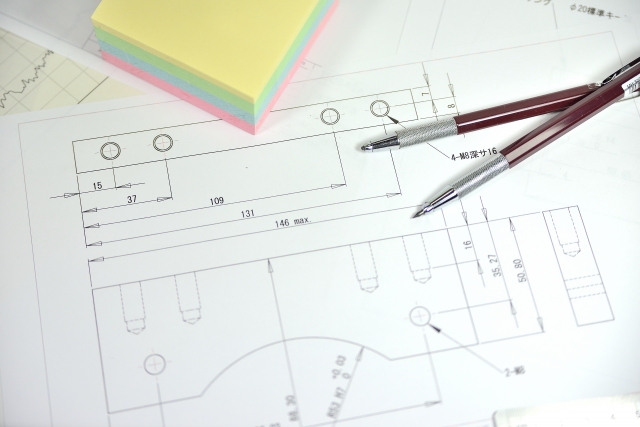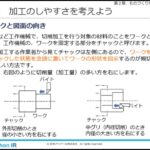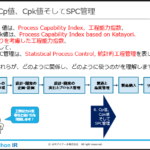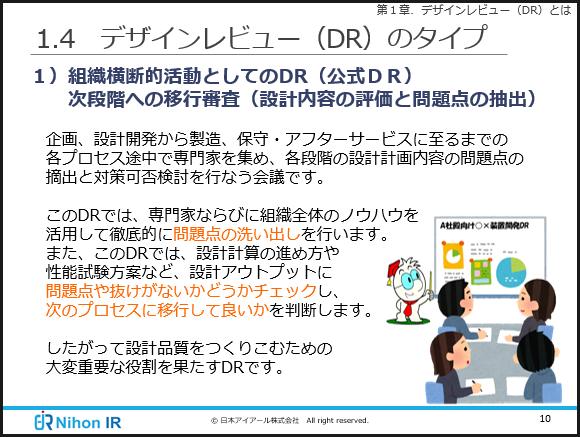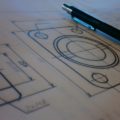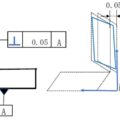《NEMA規格 vs MIL規格》防水規格選定のポイントは?

「防水設計」に関する当連載では、2回にわたって「NEMA規格入門」「MIL規格入門」をご紹介してきました。
製品開発において、NEMA規格とMIL規格のどちらを、あるいは両方を参照すべきでしょうか?
その判断は、製品の特性、ターゲット市場、そしてコストを考慮した戦略的な決定となります。
本記事では、適切な防水規格の選び方を解説します。
1.要求仕様の明確化
最適な規格を選定するための第一歩は、製品に対する要求仕様を徹底的に明確にすることです。
以下の点を自問する必要があります。
- 使用環境はどこか?:
乾燥した屋内か、水洗いされる工場か、塩害のある沿岸部の屋外か、あるいは砂漠や極地か? - 遭遇する水の形態は何か?:
結露や滴下か、ホースによる洗浄か、一時的な水没か、長期間の水没か、それとも暴風雨か? - 水以外の脅威は何か?:
塵埃、油、化学薬品、腐食性ガス、衝撃、振動、極端な温度変化、気圧変化、太陽光(紫外線)などは考慮すべきか? - ターゲット市場はどこか?:
北米の産業市場ではNEMA等級が強く要求される。欧州やアジアではIP等級が一般的。グローバル展開を目指すなら複数の規格への対応が必要になる。 - コストと開発期間の制約は?:
MIL規格の厳密なテーラリングと試験は、NEMAやIPの評価に比べて時間とコストがかかる傾向にある。
2.NEMA vs MIL:選択のシナリオ
上記の要求仕様に基づき、以下のような選択シナリオが考えられます。
NEMA規格が適する場合
- 用途:
北米向けの産業用制御盤、工作機械、食品加工設備、屋外設置の通信・電力インフラなど。 - 理由:
ターゲット市場で標準として要求されており、防水・防塵に加えて耐油性や耐腐食性といった産業環境特有の要件を明確に定義できるため。例えば、「水洗いが必要な食品工場向けなのでNEMA 4Xは必須」といった具体的な仕様決定が容易になる。
MIL規格が適する場合
- 用途:
軍事・防衛・航空宇宙関連機器、法執行機関向けの通信機器、地質調査や建設現場で使用する計測機器、そして「タフネス」をマーケティングの核とするスマートフォン、ノートPC、ウェアラブルデバイスなど。 - 理由:
水だけでなく、衝撃、振動、極端な温度など、複合的な環境ストレスに対する総合的な堅牢性が求められるため。既定の等級に当てはめるのではなく、「戦場で車両に搭載され、砂塵と振動に耐え、急な豪雨に打たれても確実に通信できる」といった具体的な運用シナリオに基づいた信頼性の実証が必要な場合に最適。
3.複数の規格への対応
グローバル市場で競争力を持つハイエンドな製品、特に過酷な環境での使用を想定したプロフェッショナル向けの製品では、複数の規格を併記することが一般的です。
例えば、ある屋外用センサーの仕様書に「IP68, NEMA 6P, MIL-STD-810H準拠(浸漬、塩水噴霧、振動、衝撃)」と記載されている場合、これは以下のような強力なメッセージを伝えます。
- IP68: 国際基準で最高の防塵・防水性能(継続的な水没)を持つ。
- NEMA 6P: 長時間の水没に加え、北米市場で重視される耐腐食性も備えている。
- MIL-STD-810H: さらに、軍事規格レベルの浸漬耐性、耐腐食性(塩水噴霧)、そして実運用で重要な振動や衝撃に対する耐性も検証済みである。
このように複数の規格を戦略的に組み合わせることで、製品の信頼性を多角的にアピールし、幅広い顧客層と市場に対してその優位性を示すことが可能になります。
4.まとめ
「NEMA規格入門」「MIL規格入門」と、今回の全3回にわたり、防水・耐環境性能を評価する二つの重要な規格、NEMA等級とMIL規格について詳細に解説しました。両者の要点を改めて整理します。
NEMA規格は、主に北米の産業用電気機器を対象としたエンクロージャの「保護等級」です。防水・防塵性能を基本としつつ、耐腐食性、耐油性、氷結といった産業現場の実情に即した多様な環境要因に対する保護レベルを明確に分類・定義しています。その評価方法は標準化されており、製造者と使用者の間で誤解のない仕様の共有を可能にします。
MIL規格(特にMIL-STD-810)は、米国国防総省が定める、極限環境下での「信頼性実証」のための規格です。最大の特徴は「テーラリング」の概念であり、製品が実際に使用される環境を想定して試験内容を個別に設計します。防水・防塵だけでなく、衝撃、振動、高低温度、高度など、機器の生存性を脅かすあらゆるストレスに対する総合的な耐性を検証することを目的としています。
この二つの規格は、優劣で語るべきものではなく、その目的と哲学が根本的に異なります。
NEMAが「どのような保護がされているか」を示すカタログスペックだとすれば、MIL規格は「どのような過酷なシナリオを生き延びられるか」を物語るストーリーと言えるでしょう。
製品開発においては、ターゲット市場、想定される使用環境、コスト、そしてマーケティング戦略を総合的に勘案し、これらの規格を適切に理解し、選択・活用することが、製品の価値を最大化し、顧客からの信頼を獲得するための鍵となります。規格の数字や文字の裏にある思想を深く読み解くことで、真にユーザーの期待に応える、堅牢で信頼性の高い製品づくりが実現するのです。
 《この記事の執筆者》
《この記事の執筆者》
鈴木崇司 講師
神上コーポレーション株式会社 代表取締役
開発QCDの最適化を追求する「匠のコンサルタント」として豊富な実績。
設計の上流工程のみならず、製造フェーズまで含めた技術支援が可能。
(※神上コーポレーションのWEBサイトはこちら)