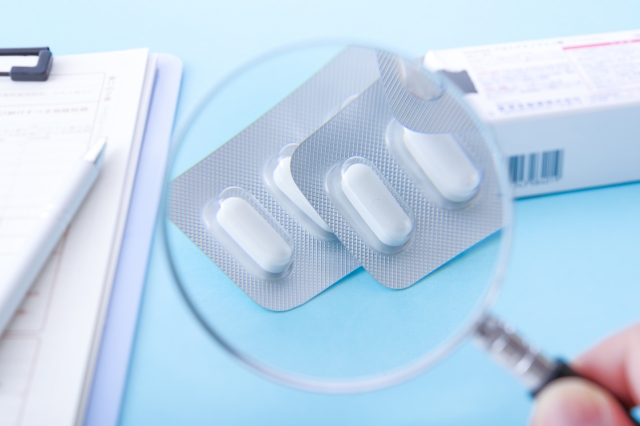<治験薬を中心に/現場目線で考える品質保証>医薬品開発プロセスに応じた規格値設定・分析法バリデーション対応・文書管理のポイント【提携セミナー】
おすすめのセミナー情報
もっと見る| 開催日時 | 2024/6/11(火) 10:30-16:30 |
|---|---|
| 担当講師 | 宮嶋 勝春 氏 |
| 開催場所 | Zoomによるオンラインセミナー |
| 定員 | - |
| 受講費 | 【オンラインセミナー(見逃し視聴なし)】:47,300円 【オンラインセミナー(見逃し視聴あり)】:52,800円 |
★治験薬の品質を中心に、医薬品開発における品質管理やバリデーション、文書管理のあり方を考える
★2023年に改訂されたICH Q9のポイントもカバー!ライフサイクルを通した品質保証の考え方とは?
<治験薬を中心に/現場目線で考える品質保証>
医薬品開発プロセスに応じた
規格値設定・分析法バリデーション対応・
文書管理のポイント
【提携セミナー】
主催:株式会社情報機構
医薬品の品質は、探索研究から始まり、Pre-formulation, 前(非)臨床試験発、臨床試験を通して、最終的な市販品の品質へと作り込まれていく。この間に、製剤処方・製造方法にとどまらず、規格として評価される品質も変化していく。この変化に適切に対応できるかどうかが、最終的な承認を得られるかどうかのカギになる。そのためには、開発各段階の目的・求められる要件を十分に理解し、その上で適切な対応が必要になる。特に、治験薬の製造・品質管理は、最終的に市販品へ繋がるものであり、各治験段階の目的に合致した段階的な品質管理の取り組みを通して最終的な市販品の品質が確立されていく、極めて重要な取り組みとなっている。この治験薬の品質は、当然のことながら製剤開発の結果であり、製剤開発にどう取り組んだのかにより、大きく影響を受けることになる。そのため、Quality by Design(QbD)に基づく開発手法について、そのポイントを十分に理解しておくことも必要となる。なお、2023年このQbDに基づく開発の根幹となるICH Q9品質リスクマネジメントガイドラインの改定が行われ、主観性の最小化が求められることとなった。
本セミナーでは、医薬品開発における段階的な品質管理・Validation(製造法、分析法)、標準物質の管理、文書管理について、特に治験段階における規格設定やValidation、標準物質の取扱いなど、現場が抱える問題に焦点を当て演者の経験を紹介するとともに、改定された品質リスクマネジメントガイドラインのポイント、知識管理・暗黙知の取扱い、そしてライフサイクルを通した品質保証の考え方について紹介する。
◆受講後、習得できること
1. 各開発段階の目的(Pre-formulation~非臨床試験~治験、申請)
2. Quality by Designにおける設計による品質の作り込みの具体的な手順
3. 主観性最小化への取り組み‐ICH Q9ガイドライン改定版のポイント:暗黙知と知識管理‐
4. ライフサイクルを通した品質保証の考え方‐Process Validationのポイント‐
5. 治験薬の品質管理を含めた開発段階に応じた規格設定・Validation・標準品の考え方
6. 主観性最小化への取り組み‐ICH Q9ガイドライン改定版のポイント‐
7. 信頼性の基準と適合性調査のポイント
◆本テーマ関連法規・ガイドラインなど
1.ICH Q8 製剤開発に関するガイドライン
2.ICH Q9(R1) 品質リスクマネジメントに関するガイドライン
3.ICH Q12 医薬品のライフサイクルマネジメントにおける技術上及び 規制上の考え方に関するガイドライン
4.治験薬の製造管理、品質管理等に関する基準(治験薬GMP)について(薬食発第0709002号平成20年7月9日)
5.ICH Q2 分析法バリデーションに関するガイドライン
6.その他
◆講演中のキーワード
Quality by Design、規格、知識管理、暗黙知、治験薬GMP
担当講師
NANO MRNA(株) 顧問 宮嶋勝春 氏
■経歴
1979年4月 ゼリア新薬工業㈱ 製剤研究所
1983年2月 米国ユタ大学薬学部留学
1985年11月 ゼリア新薬工業㈱ 中央研究所 製剤研究部
2000年3月 テルモ㈱ 研究開発センター
2006年4月 奥羽大学薬学部
2008年8月 武州製薬㈱ 製造技術部
2016年6月 一般社団法人 製剤機械技術学会事務局
2017年7月 ナノキャリア㈱ 研究部
2021年7月 ナノキャリア㈱ 監査等委員会
2023年7月 NANO MRNA㈱ 顧問
■専門および得意な分野・研究
製剤開発、GMP、査察対応
■本テーマ関連学協会での活動
製剤機械技術学会における各種委員会活動・講演・執筆、日本薬剤学会における製剤処方・プロセスの最適化検討FGなど
セミナープログラム(予定)
1.医薬品開発プロセスと臨床試験
1.1 医薬品開発プロセスのタイムテーブル・成功確率・費用等
1.2 非(前)臨床試験の役割 ‐3つの品質がポイント‐
1.3 臨床研究・臨床試験・治験・医師主導治験の違い
1.4 治験の種類と治験薬
・マイクロドーズ試験
・臨床薬理試験(Phase 1試験)
・探索的臨床試験(Phase 2試験)
・検証的臨床試験(Phase 3試験)&Pivotal試験
1.5 NDA ‐CTD:モジュール1への対応‐
2.Quality by Designに基づいた製剤開発
2.1 製剤開発の基本:品質リスクマネジメント
2.2 ICH Q9(R1)ガイドラインのポイント
‐主観性の最小化と知識管理‐
2.3 QbDに基づく製剤開発の具体的な手順
2.3.1 設計で品質を作り込むとはどういうことか
2.3.2 工程の科学的な理解を得るための具体的な方法
2.3.3 製剤の最適化に向けた具体的な手順‐Design Spaceの設定‐
・実験計画法の利用と最適化のポイント
2.4 製剤設計から製造現場へ‐QbDのPros &Cons‐
2.5 信頼性の基準への対応‐指摘事項を通してみる適合性調査へのポイント‐
2.6 ライフサイクルを通した品質への取り組み‐Process Validationへの対応‐
3.開発段階に応じた品質管理‐規格・Validation・文書管理‐
3.1 医薬品の品質とは何か?‐規制文書にみる品質の定義‐
3.2 品質はどこで、どうやって設定されるのか
3.3 医薬品品質の段階的な対応‐規格及び規格値設定とその根拠‐
3.3.1 医薬品の品質とは何か‐品質は規格で表すのか‐
3.3.2 3通りの規格:出荷規格、Reported Results、For Information Only
3.3.3 規格設定方法‐工程情報に基づく設定から科学的な根拠に基づく設定へ‐
3.3.4 非臨床試験用製剤の規格及び規格値設定の考え方と具体的な設定事例
3.3.5 Phase 1~3用治験薬の規格及び規格値設定の考え方と具体的な設定事例
3.3.6 バイオシミラーを含むバイオ医薬品の品質評価のポイント
3.4 開発段階に応じた分析法・分析法Validationへの対応
3.4.1 非(前)臨床、Phase 1~3治験段階における分析法Validationへの対応‐具体的な対応事例‐
3.4.2 承認申請とICH 分析法バリデーションガイドラインへの対応
3.4.3 分析法の変更管理のポイント
3.5 原薬・製剤に含まれる不純物、そして標準物質(品)への対応
3.5.1 開発段階に応じた不純物の管理‐試験法開発を含む‐
3.5.2 標準物質/標準品の開発スケジュールとSOP
3.5.3 標準物質(品)に求められる品質と作成手順
3.5.4 不純物の標準物質(品)にどう対応すべきか
3.6 治験薬GMPへの対応
3.6.1 治験薬GMP通知(2008年)のポイント
3.6.2 Validationで対応すべきか、Verificationで対応すべきか‐Validation:3Lots製造の誤解‐
3.6.3 開発段階における原材料・文書管理
4.治験薬の委託製造
4.1 治験薬の委託製造におけるポイント-組織・文書・人材-
4.2 技術移転とトラブル対応-トラブル事例を中心に-
4.3 交叉汚染対策-洗浄バリデーションへの対応-
5.医薬品の品質保証のあるべき姿とは?
5.1 規則・SOPだけでは品質を保証することができない‐過去の不祥事に学ぶ‐
5.2 品質システムとQuality Culture ‐Quality Cultureとコストの関係‐
6.まとめ
公開セミナーの次回開催予定
開催日
2024年6月11日(火) 10:30-16:30
開催場所
Zoomによるオンラインセミナー
受講料
【オンラインセミナー(見逃し視聴なし)】:1名47,300円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき36,300円
【オンラインセミナー(見逃し視聴あり)】:1名52,800円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき41,800円
*学校法人割引;学生、教員のご参加は受講料50%割引。
●録音・撮影行為は固くお断り致します。
備考
※配布資料等について
●配布資料はPDF等のデータで配布致します。ダウンロード方法等はメールでご案内致します。
- 配布資料に関するご案内は、開催1週前~前日を目安にご連絡致します。
- 準備の都合上、開催1営業日前の12:00までにお申し込みをお願い致します。
(土、日、祝日は営業日としてカウント致しません。) - セミナー資料の再配布は対応できかねます。必ず期限内にダウンロードください。
●当日、可能な範囲でご質問にお答えします。(全ての質問にお答えできない可能性もございます。何卒ご了承ください。)
●本講座で使用する資料や配信動画は著作物であり、無断での録音・録画・複写・転載・配布・上映・販売などは禁止致します。
お申し込み方法
★下のセミナー参加申込ボタンより、必要事項をご記入の上お申し込みください。
★【オンラインセミナー(見逃し視聴なし)】、【オンラインセミナー(見逃し視聴あり)】のいずれかから、ご希望される受講形態をメッセージ欄に明記してください。