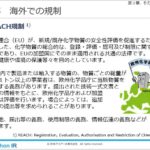【技術系資格ナビ】高圧ガス製造保安責任者 [難易度/試験対策/メリットなど]

「高圧ガス製造保安責任者」は、高圧ガスを安全に製造・管理するために必要な国家資格です。産業界で重要な役割を担うこの資格は、危険物を扱う現場や化学プラント、製造工場などで広く必要とされています。
本記事では、高圧ガス製造保安責任者の資格概要、試験の内容と効果的な勉強方法について解説します。
目次
「高圧ガス製造保安責任者」とは
高圧ガス製造保安責任者という資格は、「高圧ガス保安法」(略称:高圧法)という法律に基づいて設けられています。この法律は、昭和26(1951)年に制定され、日本国内での高圧ガスの「製造」「販売」「輸送」「消費」に関する安全を確保することを目的としています。
高圧ガスは、エネルギー源や化学原料として非常に有用である一方で、適切に取り扱わなければ爆発や中毒といった重大事故につながる危険性もあります。そこで、特定の設備や対象となるガスの取り扱いに対しては、有資格者を配置し、保安管理を徹底することが義務づけられています。
高圧ガス保安法は産業と社会の安全を守るための根幹をなす法律であり、保安責任者はその運用の最前線に立つ存在です。
現場での役割と業務の具体例
高圧ガス製造保安責任者は、実務において重要な役割を担います。以下にその業務内容の一例を紹介します。
日常的な業務
- 保安点検の実施と記録: ガス漏れ検査、配管の腐食チェック、圧力計の点検など
- 設備保守管理: バルブやタンク、冷却装置などの正常作動確認や定期的なメンテナンス
- 作業手順書・マニュアルの作成および改訂: トラブルや作業改善に対応する文書整備
- 関係者への教育訓練: 新入社員や作業者への安全講習や注意喚起の実施
異常時対応
- ガス漏れ・設備故障の初期対応: 遮断弁の閉鎖、避難誘導、消防署や行政への連絡
- 事故報告書の作成: 原因分析と再発防止策の提言を含む文書の提出
その他の責務
- 保安検査の立会いと対応: 定期検査や行政による監査への対応
- 申請・届出業務: 新設備設置時の許可申請や変更届などの法定手続き
このように保安責任者は“安全管理の専門家”として高圧ガスを取り扱う現場を支える存在です。企業にとっても非常に重要な役割といえます。
「高圧ガス製造保安責任者」の資格概要
国家資格必置資格の目的
上述のように高圧ガス製造保安責任者は、「高圧ガス保安法」に基づいて設けられた国家資格であり、高圧ガスの製造・貯蔵・移送などに関する保安管理を行う責任者です。ガス漏れや爆発などの重大事故を未然に防ぐため、専門的な知識と技術が求められます。
資格の種類
高圧ガス製造保安責任者は、製造するガスの種類や製造方法に応じて以下のように区分されています。
- 甲種化学、甲種機械:
高圧ガス製造事業所において、高圧ガスの製造に関する保安の統括的な業務を行う上で必要な資格です。ガスの種類や製造規模による制限はありません。 - 乙種化学、乙種機械:
高圧ガス製造事業所において、高圧ガスの製造に関する保安の統括的又は実務的な業務を行う上で必要な資格で、高圧ガスの種類について制限はありませんが、保安技術管理者に選任される場合には、高圧ガスの処理能力が1日に100万立方メートル未満の事業所に限られます。 - 丙種化学(液化石油ガス):
LPガス製造事業所において、LPガスの製造に関する保安の統括的又は実務的な業務を行う上で必要な資格です。保安技術管理者に選任される場合には、LPガスの処理能力が1日に100万立方メートル未満の事業所に限られます。 - 丙種化学(特別試験科目):
製造に係る保安の実務的な業務を行う方に必要な資格で、保安係員のみに選任され、高圧ガスの製造施設に関する保安に携わることができます。 - 第一種冷凍機械(大型):
大型冷凍空調機器を備えている施設、冷凍倉庫、冷凍冷蔵工場等において、製造(冷凍)に関する保安の実務を含む統括的な業務を行う上で必要な資格です。
冷凍能力に関する規模の制限はありません。 - 第二種冷凍機械(中型):
1日の冷凍能力が300トン未満の製造施設に関する保安に携わることができます。 - 第三種冷凍機械(小型):
1日の冷凍能力が100トン未満の製造施設に関する保安に携わることができます。
資格の必要性
特定の製造設備を持つ事業者は、法律上、必ず有資格者を配置する必要があります。そのため、業界では常に有資格者の需要が高く、キャリアアップにも有利となります。
「高圧ガス製造保安責任者」の試験
会場試験実施試験実施者
- 甲種化学、甲種機械、第一種冷凍機械: 経済産業大臣
- 乙種化学、乙種機械、第二種冷凍機械、第三種冷凍機械: 都道府県知事
受験資格
学歴や実務経験には関係なく、誰でも受験することができます。
【試験科目】
- 甲種化学、甲種機械、第一種冷凍機械:
法令(択一式)、保安管理(択一式)、学識(記述式) - 乙種化学、乙種機械、丙種化学、第二種冷凍機械:
法令(択一式)、保安管理(択一式)、学識(択一式) - 第三種冷凍機械:
法令(択一式)、保安管理(択一式)
高圧ガス保安協会(KHK)が実施する3日間の講習を受講し、検定試験に合格すると、「学識」と「保安管理技術」の科目が免除されますが、法令に関する試験は必須です。
試験合格基準
各科目60点以上、1科目でも60点に達しない科目があると不合格となります。
【合格率の目安と難易度】
年度や区分によって異なりますが、おおよその合格率は、甲種化学、甲種機械、乙種化学、乙種機械の各分野において以下のようになっています。
- 全科目受験の場合で 20~30%
- 学識と保安管理免除(講習受講、検定合格)の場合で 70~80%
KHKが実施する3日間講習を受講の上、技術検定に合格して学識と保安管理の試験が免除となることによって、試験合格率は格段に高くなっています。
試験の難易度としては、技術系国家資格の中では中~やや高めなレベルです。出題範囲は法令、化学工学、安全管理など多岐にわたり、特に実務経験が少ない受験者にとっては理解が難しい内容も含まれますので、十分な事前学習と過去問演習が不可欠です。
独学の場合の勉強方法
教材について
KHKが実施する講習を受講せずに、独学で合格を目指す場合は、次のような教材の活用が効果的です。
- 高圧ガス保安法に関する解説書
- 『高圧ガス保安技術』(KHK公式・市販)
- 『過去問題集』(KHK公式・市販)
学習スケジュールについて
計画的な学習が合格の鍵です。試験日から逆算して3〜6か月の学習期間を確保し、週単位のスケジュールを組むとよいでしょう。
※スケジュールの例
- 1〜2ケ月目: 法令・基礎理論の理解
- 3〜4ケ月目: 応用問題・計算問題
- 5ケ月目以降: 過去問・模擬試験で実践力アップ
過去問を使って本番と同じ形式で模擬試験を実施することで、時間配分や解答スピードを養えます。
また、過去問を繰り返すことにより「頻出テーマ」を把握することも可能です。
主な学習内容
乙種化学・乙種機械受験者向けの「高圧ガス保安技術(中級)」を例にとると、次のような内容が記載されています。
- ① プラントの通常運転時における温度(常用の温度)において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ)が1MPa以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く)であって、かつ、現にその圧力が1MPa以上であるもの、あるいは密閉容器内などで現にその圧力が1MPa未満であっても、温度が35℃において圧力が1MPa以上となる圧縮ガス
- ② プラントの通常運転時における温度(常用の温度)において圧力が0.2MPa以上となる圧縮アセチレンガスであって、かつ、現にその圧力が0.2MPa以上であるもの、あるいは密閉容器内などで現にその圧力が0.2MPa未満であっても、温度が15℃において圧力が0.2MPa以上となる圧縮アセチレンガス
- ③ プラントの通常運転時における温度(常用の温度)において圧力が0.2MPa以上となる液化ガスであって、かつ、現にその圧力が0.2MPa以上であるもの、あるいは温度が35℃以下において、圧力(飽和蒸気圧)が0.2MPaとなる液化ガス
- ④ 上記③に掲げたものを除いて、温度35℃(現にその温度が35℃以下でもよい)において圧力(飽和蒸気圧)が0MPaを超える液化ガスのうち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル、液化酸化エチレン
- 1).気体の性質
ボイル・シャルルの法則、状態方程式、熱容量、蒸気圧・沸点、体積膨張係数、など - 2).気体の熱力学
熱力学の第一法則、エンタルピ―、熱力学の第二法則、エントロピー、気体の状態変化、カルノーサイクル、熱力学線図、など - 3).気体の化学反応
化学反応式、反応熱、反応速度、など - 4).燃焼・爆発
燃焼・爆発とは、反応と発火、危険性の評価、影響と事故例、など - 5).ガス各論
可燃性ガス・支燃性ガス、毒性ガス、不燃性ガス、フルオロカーボン、特殊高圧ガス - 6).流動・電熱・分離
流体の流れ、圧力、円管内の流れ、レイノルズ数、連続の式、ベルヌーイの定理、管摩擦、熱伝導、熱伝達、放射、など - 7).材料の力学と強度
応力とひずみ、フックの法則、応力‐ひずみ線図、強度と破壊、許容応力と安全率、など - 8).高圧装置用材料
化学結合と結晶、金属材料(炭素鋼、低合金鋼、ステンレス鋼、非鉄金属)、高温用材料、低温用材料、非金属材料、など - 9).材料の劣化
腐食(異種金属接触腐食、孔食、すき間腐食、粒界腐食、など)、乾食(酸化、硫化、など)、防食、摩耗とエロージョン、など - 10).高圧設備
溶接、非破壊試験、高圧装置(塔槽、貯槽、熱交換器、管・管継手・バルブ、など)、計装(計器、制御システム、安全計装)、圧縮機・ポンプ・冷凍機、漏洩防止、など
高校の物理・化学、高専・工科系大学(機械工学・応用化学)で学ぶ内容が多く登場します。学生時代の教科書・参考書を参照しながら勉強しましょう。
- 1).安全設計・管理
工場レイアウト、建屋の安全設計、安全理論、安全性評価、安全性解析、リスクマネジメント、安全組織、保安教育訓練、防災管理、など - 2).保安・防災設備
電気設備(電気設備、防爆、保安電力、接地など)、保安装置(安全装置、緊急遮断装置など)、防災設備(消火、火災報知、ガス漏洩検知、危険事態発生防止、など) - 3).運転管理
運転基準、定常運転、誤操作防止、漏洩防止、など - 4).設備管理
体制、設備診断・検査、工事管理 - 5).高圧ガス関連の災害事故
1)~4)については、高圧ガス製造設備のみならず、広く製造設備全般に適用することが可能な内容となっています。
資格取得後のメリット
- 就職・転職での優位性:
高圧ガス製造保安責任者は、化学・エネルギー・鉄鋼・半導体など多様な業界で高い評価を受ける資格です。製造部門の管理者や安全管理責任者として就職や転職を行う際にも非常に有利な資格です。 - 昇進・昇格への寄与:
企業によっては、資格取得が主任技術者・係長クラス以上への昇進条件になっている場合もあります。業務の幅が広がることで、年収アップも見込まれます。 - 自己成長・技術力向上:
資格取得の過程で得た知識は、実務でも大きな武器になります。安全意識の向上と技術的な自信が、職場での信頼を高める要因となります。
まとめ
高圧ガス製造保安責任者は、高度な専門性と責任を伴う国家資格であり、多くの業界で需要があります。試験に合格するには、的確な教材選びと継続的な学習、そして実践的な問題演習が不可欠です。
取得後は、キャリアの選択肢が広がり、企業内での評価も向上します。将来性の高い資格として、これからの技術者・保安管理者を目指す方にはぜひ挑戦してみてください。
(アイアール技術者教育研究所 S・Y)












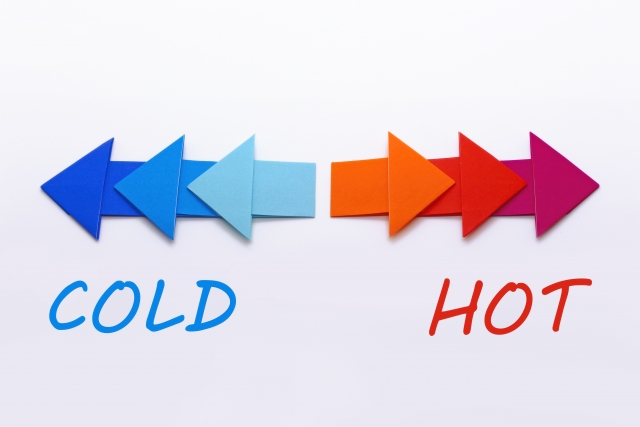

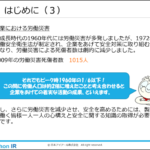
](https://engineer-education.com/wp/wp-content/uploads/2019/06/facility_PM-150x150.png)