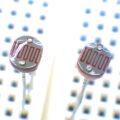【医薬品製剤入門】腸溶性製剤の基礎知識[特徴/製法/試験法など]
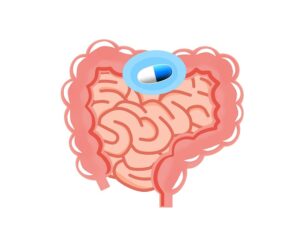
「腸溶性製剤」は、製剤に工夫をすることによって、胃では溶けずに腸で溶けるようにした製剤をいいます。
形状としては、錠剤、カプセル、顆粒剤があります。腸で溶けることによっていろいろなメリットがある製剤になっています。
今回は、腸溶性製剤についてまとめてみました。
目次
1.腸溶性製剤とは
薬の中には、胃酸によって分解されたりして、効果が失われる薬や、胃にダメージを与えたり、吸収される場所が腸(小腸)に限定される薬などがあります。
腸溶性製剤は、そのような薬物などに対して製剤的な技術を施し、主に小腸内で放出するよう設計された製剤です。作用時間を遅くしたい場合にも腸溶性製剤とすることがあります。
日本薬局方では、[3] 製剤各条に「腸溶性製剤」として、次のように記載されています。
「1.経口投与する製剤
(2) 経口投与する放出調節製剤は,固有の製剤設計及び製法により放出性を目的に合わせて調節した製剤で,腸溶性製剤,徐放性製剤などが含まれる.
(ⅰ) 腸溶性製剤
腸溶性製剤は,有効成分の胃内での分解を防ぐ,又は有効成分の胃に対する刺激作用を低減させるなどの目的で,有効成分を胃内で放出せず,主として小腸内で放出するよう設計された製剤である.本剤を製するには,通例,酸不溶性の腸溶性基剤を用いて皮膜を施す.腸溶性製剤は,有効成分の放出開始時間を遅らせた放出調節製剤である放出遅延製剤に含まれる.」
また、各剤形では次のように記載されています。
「1.1錠剤
(2) 本剤を製するには,・・・また,適切な方法により,腸溶錠・・とすることができる.」
「1.2. カプセル剤
(2) 本剤を製するには・・・また,適切な方法により,・・腸溶性カプセル剤・・とすることができる.」
「1.3. 顆粒剤
(2) 本剤を製するには・・また,適切な方法により,・・腸溶性顆粒剤とすることができる.」
2.腸溶性製剤の特徴(メリット・デメリット)
腸溶性製剤は、下記のようなメリットがある製剤です。
- 胃の刺激を避ける:特定の薬剤は、胃の中で分解されると効果が減弱する場合があります。このような薬剤を腸溶性製剤にすることで、胃の刺激を避けて、腸で吸収されるようにします。
- 胃酸による分解を防ぐ:胃酸は、一部の薬剤の分解を早める原因となることがあります。腸溶性製剤は、このような薬剤が胃酸によって分解されるのを防ぐために使用されます。
- 薬剤の効果のタイミングを制御する:腸溶性製剤は、薬剤が腸に達してから効果を発揮するため、効果の持続時間やタイミングを制御するのに役立ちます。 等々
ただし、下記のようなデメリットもあります。
- 噛んだり砕いたりすると、胃酸によって効果を失ったり、胃の表面を荒らす原因になったりする。
- 効果が発現するまでに時間がかかるため、即効性が求められる場合には適さないことがある。
- 腸溶性製剤には特殊な製造技術が必要であり、その製造コストが他の一般的な製剤よりも高い場合がある。 等々
3.腸溶性錠剤の製造方法
腸溶性にする方法としては、低pHでは溶けず中性付近で溶解する高分子ポリマーなどを用いてコーティングする方法が一般的のようです。
腸溶錠の製法としては、日本薬局方に下記の記載があります。
「1.1. 錠剤
(2) 本剤を製するには,通例,次の方法による.また,適切な方法により,腸溶錠又は徐放錠とすることができる.
(i) 有効成分に賦形剤,結合剤,崩壊剤などの添加剤を加えて混和して均質とし,水又は結合剤を含む溶液を用いて適切な方法で粒状とした後,滑沢剤などを加えて混和し,圧縮成形する.(以下略)」
4.腸溶性錠剤の添加物
腸溶性製剤に用いられる添加剤としては、ヒプロメロースフタル酸エステルや酢酸フタル酸セルロース、メタクリル酸コポリマーなどがあります。
小腸の中性条件で溶解するコーティング剤として用いられます。
5.腸溶性錠剤の試験法
日本薬局方では、医薬品として製造された腸溶性製剤が下記試験法に適合することが定められています。
(1)製剤均一性試験法
個々の製剤間での有効成分量の均一性の程度を示すための試験法です。
有効成分の含量が、表示量の一定範囲内にあることを確認し、均一性を保証します。
製剤含量の均一性は、含量均一性試験又は質量偏差試験のいずれかの方法で試験されることになっています。
第十七改正日本薬局方6.02に詳細な試験法が記載されています。
(2)溶出試験法
経口製剤について溶出試験規格に適合しているかどうかを判定するために、また、著しい生物学的非同等を防ぐことを目的としている試験です。
腸溶性製剤、即放性製剤、徐放性製剤などによって試験方法、判定法が定められています。
第十七改正日本薬局方6.10に詳細な試験法が記載されています。
「3.1.3. 腸溶性製剤
(ⅰ) 操作:別に規定するもののほか,溶出試験第1液による試験及び溶出試験第2液による試験について,それぞれ独立して即放性製剤の項と同じ操作を行う.
(ⅱ) 試験液:溶出試験第1液による試験;試験液に溶出試験
第1液を用いるほかは即放性製剤の項における指示に従う.溶出試験第2液による試験;試験液に溶出試験第2液を用いるほかは,即放性製剤における指示に従う.
(ⅲ) 試験時間:溶出試験第1液による試験;通例,錠剤,カプセルは2時間,顆粒は1時間とする.溶出試験第2液による試験;即放性製剤の項と同じ.試験液は規定時間の±2%以内に採取する.」
(3)崩壊試験法
腸溶性製剤が試験液中、定められた条件で規定時間内に崩壊するかどうか否かを確認する試験法です。
製造工程のバラツキが小さいことを確認するための品質管理が主目的としています。
第十七改正日本薬局方6.09に詳細な試験法が記載されています。
「2.2.1. 腸溶錠及び腸溶性カプセル剤
(ⅰ) 崩壊試験第1液による試験:試験液に崩壊試験第1液を用いて120分間,即放性製剤の操作法に従って試験を行う.腸溶錠及び腸溶性カプセル剤が壊れた場合,又は腸溶性皮膜が開口,破損した場合,崩壊したものとする.全ての試料が崩壊しない場合,適合とする.1個又は2個が崩壊した場合は,更に12個の試料について試験を行い,計18個の試料のうち16個以上の試料が崩壊しない場合,適合とする.
(ⅱ) 崩壊試験第2液による試験:試験液に崩壊試験第2液を用いて60分間,即放性製剤の操作法に従って試験を行い,崩壊の適否を判定する.
2.2.2. 腸溶顆粒剤及び腸溶顆粒を充塡したカプセル剤 (以下略)」
6.腸溶性錠剤の医薬品
添付文書情報で、腸溶性製剤を調べてみると、以下のようになりました。
- 種類 : 腸溶性製剤(腸溶錠、カプセル等)
- 医薬品数(*) :63以上
- 主な医薬品 : 「ランソプラゾール腸溶錠」「オメプラール腸溶錠」「アスピリン腸溶錠」等々
(*)医薬品数はジェネリック医薬品なども含みます。
7.腸溶性製剤に関する特許・文献調査
(1)腸溶性製剤に関する特許検索
J-Platpatを用いて腸溶性製剤の特許を調査してみました。(調査日:2023.7.27)
① キーワードによる検索
- 腸溶性/CL ⇒ 1894件
- 腸溶性製剤/CL ⇒ 75件
- 腸溶性/CL*A61K/FI ⇒ 1824件
② 国際特許分類(IPC)による検索
腸溶性製剤の特許を見てみると、A61K31[有機活性成分を含有する医薬品製剤[2]]が多く付与されているようです。
これらはおそらく腸溶性製剤に添加物として用いられているポリマーによるものと考えられます。
調査目的によって使うことができる場合があると思います。
② Fタームによる検索
4C076[医薬品製剤]に腸溶性のコード4C076FF25[目的,機能 ・被覆剤 ・・水溶性 ・・・腸溶性]があります。
- 4C076FF25/FT ⇒ 2159件
これらの中には、「フマル酸ジメチルを含有する腸溶性錠剤」「腸溶性の粒状物及びそれを含有する固形製剤」「腸溶性硬質カプセル」「腸溶性コーティング用組成物及び固形製剤の製造方法」等々の特許が見受けられました。
(2)腸溶性製剤に関する文献調査
J-STAGEを用いて文献調査を行ってみました。(調査日:2023.7.27)
- 全文検索: 腸溶性製剤 ⇒ 196件
- 抄録検索: 腸溶性製剤 ⇒ 3件
- 全文検索: 腸溶性製剤 and 医薬 ⇒ 133件
「腸溶性錠剤の崩壊試験法に関する研究」「ニフェジピンと腸溶性コーティング剤から成る固体分散について(第1報)溶出挙動」「腸溶性ニフェジピン固体分散体の溶解機構について」などの文献が見られました。
これらの文献の内容を確認したい方は、ぜひ各データベースを検索してみましょう。
ということで今回は、「腸溶性錠剤」に関する基礎知識をご紹介しました。
(日本アイアール株式会社 特許調査部 S・T)



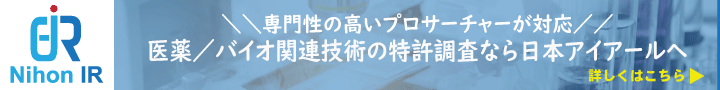





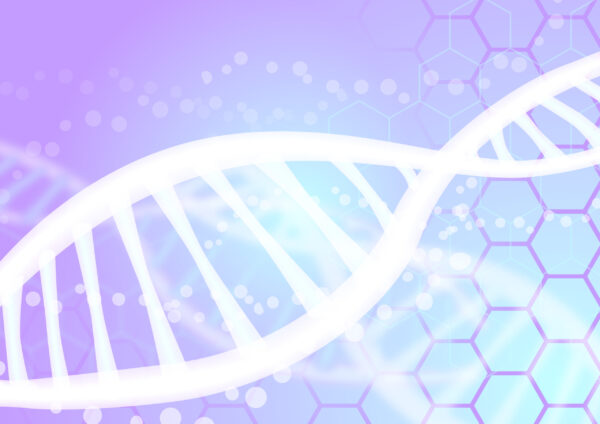
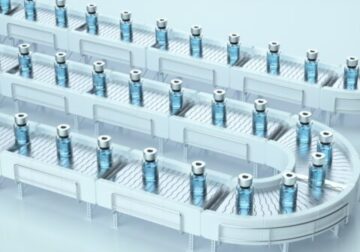


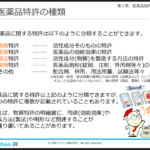
](https://engineer-education.com/wp/wp-content/uploads/2024/01/solubilizer-150x150.png)