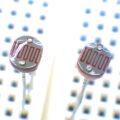【医薬品製剤入門】カプセル剤の基礎知識・まとめ解説

カプセル剤は、よく処方される剤形といえますが、苦くないという利点があるものの、少ない水で飲もうとすると、のどに張り付いたりした経験をお持ちの方も多いかと思います。
今回は、医薬品製剤のうち、カプセル剤の基礎知識についてご紹介します。
目次
1.カプセル剤とは?
日本薬局方では、カプセル剤を以下のように説明しています。
“(1) カプセル剤は,経口投与する,カプセルに充塡又はカプセル基剤で被包成形した製剤である.本剤には,硬カプセル剤及び軟カプセル剤がある.”
カプセル剤には、硬カプセル剤(ハードカプセル)と軟カプセル剤(ソフトカプセル)があります。
(1)硬カプセル
キャップとボディからなり、粉末、液体、顆粒などの医薬品(製剤)を充てんしたボディにキャップを被せて造ります。
大きさは、9号、5号、4号、3号、2号、1号、0号、00号、000号などの規格があります。
そのうち、3号・4号が多く使われています。
4号は大きさが0.5×14.0㎜、内容量は0.20cc/0.06gで、3号は大きさが0.5×15.5㎜、内容量は0.27cc/0.12gとなっています。
(2)軟カプセル
主に液状の添加剤に溶解または分散したものを、ゼラチン等の基剤で包み込んで造ります。
油状液を固形剤にすることに適しています。
通常は硬カプセルに比べて弾力があります。
2.カプセル剤のメリット・デメリットは?
カプセル剤には、下記のようなメリットがある製剤です。
- 錠剤に比べて添加剤、製造工程数が少ない
- 熱や圧力を加えずに製剤化が可能
- 液状のものでも製剤化が可能
- 水や酸素による分解を抑制できる(安定性の向上)
- 含量均一性が高い、微量活性成分も製剤化が容易に可能となる
- 味やにおいのマスキングが可能
- 印刷・カラーバリエーションによる識別化が可能(硬カプセル) など
一方、デメリットとしては、
- 錠剤に比べて高価になる
- 湿度の影響を受けやすい薬物には向かない
- ・飲み込みづらい、のどに違和感を生じやすい(硬カプセル) など
といった点が挙げられます。
3.カプセル剤の製造方法
カプセルの製法としては、日本薬局方に下記の記載があります。
“(2) 本剤を製するには,通例,次の方法による.また,適切な方法により腸溶性カプセル剤又は徐放性カプセル剤とすることができる.カプセル基剤に着色剤,保存剤などを加えることができる.
(ⅰ) 硬カプセル剤
硬カプセル剤は,有効成分に賦形剤などの添加剤を加えて混和して均質としたもの,又は適切な方法で粒状若しくは成形物としたものを,カプセルにそのまま又は軽く成形して充塡して製する.
(ⅱ) 軟カプセル剤
軟カプセル剤は,有効成分に添加剤を加えたものを,グリセリン又はD-ソルビトールなどを加えて塑性を増したゼラチンなどの適切なカプセル基剤で,一定の形状に被包成形して製する.”
この日本薬局方の記載に、若干の説明を付け加えます。
まず、硬カプセルについては、ボディに医薬品(製剤)を充てんする自動充填機には、「オーガー式」、「ダイコンプレス式」など、種々のタイプがあり、内容物の物性によって選択します。
また、キャップとボディに凹凸を設けてしっかりと結合を強くしたり、結合部に沿って帯状にシール(バンドシール法)したり、水エタノール混合液をスプレーして加熱溶着(マイクロスプレー法)させ、カプセルが外れないような工夫もされています。
軟カプセルについては、皮膜内部に内容物を充填することにより製造されますが、皮膜の形成と充填工程が同時に行われます。「ロータリー式」と「シームレス式」があります。
「ロータリー式」は、一対の円筒状の金型(ダイロール)を用いて軟カプセルを連続的に成型する方法です。
「シームレス式」は、同心円ノズルを用いて内容物を被膜液で被包する方法で、カプセルの継ぎ目がない(シームレス)、粒状であることが特徴です。
4.カプセル剤に用いる主な膜基剤・添加物
(1)硬カプセルの膜基剤・添加物
カプセルの基剤は、ゼラチン、ヒプロメロース、プルンなどが用いられます。
ゼラチンは、水分が低下すると被膜強度が低下しますので、内容物の吸湿性が高い場合はカプセルの割れが発生する原因となります。ただし、ゼラチンにポリエチレングリコールを添加することで被膜強度を改善することができるとされてます。
硬カプセル剤の内容物(製剤)に用いられる添加剤は、錠剤や顆粒剤などと同様な添加剤が用いられますが、硬カプセル剤製造において最も重要な要素は流動性であることから、流動性に適した添加剤を選択します。
また、充填環境である温度、湿度に影響を受けやすいことにも注意が必要です。
代表的な添加剤としては、希釈剤(結晶セルロースや乳糖など)、流動化剤(ケイ酸塩類、タルク)、崩壊剤(コーンスターチ、クロスカルメロースナトリウム)、湿潤剤(ラウリル硫酸ナトリウム、ポリソルベート)、滑沢剤(タルク、ステアリン酸マグネシウム)などがあります。
(2)軟カプセルの膜基剤・添加物
軟カプセルの基剤は、ゼラチン、デンプン、カラギーナンが用いられています。
被膜液は、ゼラチンに精製水、グリセリンやソルビトールを等の可塑剤を添加、加熱混合して調製されます。
内容物(製剤)の添加剤としては、植物油、中鎖脂肪酸トリグリセリド、レシチン、ポリエチレングリコール、プロピレングリコールまたはその脂肪酸エステル類が用いられることが多いようです。
軟カプセルの場合は、添加剤よりも充填環境が重要で、特にゼラチンの物性変化には注意が必要になります。
5.カプセル剤に関する製剤試験法
日本薬局方では、医薬品として製造されたカプセルが下記試験法に適合することが定められています。
(1)製剤均一性試験法
個々の製剤間での有効成分量の均一性の程度を示すための試験法です。
有効成分の含量が、表示量の一定範囲内にあることを確認し、均一性を保証します。
製剤含量の均一性は、含量均一性試験又は質量偏差試験のいずれかの方法で試験されることになっています。
第17改正日本薬局方6.02に詳細な試験法が記載されています。
(2)溶出試験法
経口製剤について溶出試験規格に適合しているかどうかを判定するために、また、著しい生物学的非同等を防ぐことを目的としている試験です。
腸溶性製剤、即放性製剤、徐放性製剤などによって試験方法、判定法が定められて今す。
第17改正日本薬局方6.10に詳細な試験法が記載されています。
(3)崩壊試験法
カプセルが試験液中、定められた条件で規定時間内に崩壊するかどうか否かを確認する試験法です。
製造工程のバラツキが小さいことを確認するための品質管理が主目的としています。
第17改正日本薬局方6.09に詳細な試験法が記載されています。
6.カプセル剤の医薬品(硬/軟カプセルの数と主な医薬品)
添付文書情報で、どのようなカプセル剤があるか調べてみました。
| カプセル種類 | 医薬品数* | 主な医薬品 |
| 硬カプセル | 390以上 | 「アジスロマイシンカプセル小児用」「アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル」「ケトチフェンカプセル」「セフジニルカプセル」「タクロリムスカプセル」「テプレノンカプセル」等多数 |
| 軟カプセル | 150以上 | 「アルファカルシドールカプセル」「イコサペント酸エチルカプセル」「カルシトリオールカプセル」「シクロスポリンカプセル」「デュタステリドカプセル」「ナルフラフィン塩酸塩カプセル」「メナテトレノンカプセル」等多数 |
(*)医薬品数はジェネリック医薬品なども含みます。
7.カプセル剤に関する特許・文献の調査
(※いずれも2021年3月22日における検索結果です)
(1)カプセル剤に関する特許検索
日本特許庁の「J-Platpat」を用いての特許を調査してみました。
① キーワード検索
- カプセル/CL*A61K/FI ⇒ 16399件
(※医薬品に関するメインの分類(FI)の「A61K」に限定しています。)
② IPC(国際特許分類)による検索
カプセル剤に対応するIPC分類としては、「A61K9/48」(※特別な物理的形態によって特徴づけられた医薬品の製剤 ・カプセル製剤,例.ゼラチン製のもの,チョコレート製のもの[2])がありますので、これを用いて検索してみます。
- A61K9/48/IP ⇒ 14873件
③ Fタームによる検索
カプセルを含むFタームとしては、「4C076AA53」(※4C076 医薬品製剤:形態 ・カプセル製剤)がありますので、これを用いて検索してみます。
- 4C076AA53/FT ⇒ 16515件
また、「4C076AA53」の下位概念として、次のようなFタームがありますので、検索してみました。
調査対象のカプセルについて種類が明確となっている場合は、これらのFタームを利用してみましょう。
- ハードカプセル:4C076AA54/FT ⇒ 2426件
- ソフトカプセル:4C076AA56/FT ⇒ 1868件
- シームレスカプセル:4C076AA57/FT ⇒ 191件
- 被覆カプセル:4C076AA60/FT ⇒ 709件
- ミクロカプセル:4C076AA61/FT ⇒ 6040件
カプセル剤の製法に関するものとして、以下のようなFタームもあります。
- マイクロカプセル: 4C076GG21/FT ⇒ 2709件
- カプセルのシーリング: 4C076GG37/FT ⇒ 108件
(2)カプセル剤に関する文献調査
J-STAGEを用いて文献調査を行ってみました。(調査日:2021.3.22)
- 全文検索: カプセル ⇒ 20020件
- 抄録検索: カプセル ⇒ 1162件
- 全文検索: カプセル and 医薬 ⇒ 3460件
- 抄録検索: カプセル and 医薬 ⇒ 31件
「生理活性物質のマイクロカプセル化と用途開発」「ビフィズス菌を配合した機能性食品への腸溶性シームレスカプセルの利用」「OE-7 (ステアリン酸エリスロマイシンカプセル) に関する研究」といったタイトルの文献が見られました。
上記検索で得られる特許情報や文献の内容を見てみたい方は、各データベースからご確認ください。
(日本アイアール株式会社 特許調査部 S・T)



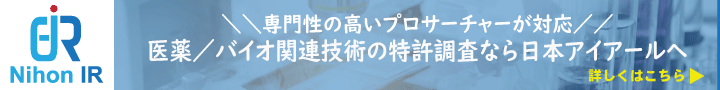





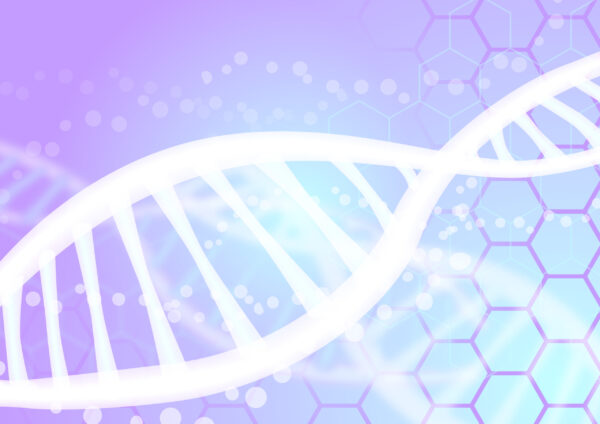
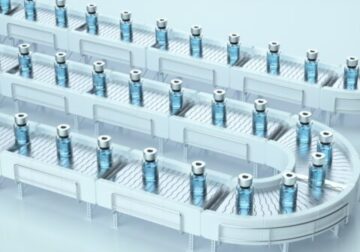


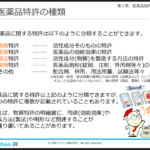
](https://engineer-education.com/wp/wp-content/uploads/2024/01/crushing-150x150.png)