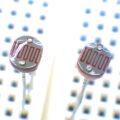吸着等温線を用いた各種吸着材料の性能評価とデータの解釈【提携セミナー】
| 開催日時 | 未定 |
|---|---|
| 担当講師 | 遠藤 明 氏 |
| 開催場所 | 未定 |
| 定員 | 未定 |
| 受講費 | 未定 |
★ CO2、メタン、PFAS、VOCなどを吸着する材料の吸着量、吸着速度を正確に測定し、材料設計・開発へ活かす!
吸着等温線を用いた各種吸着材料の性能評価とデータの解釈
【提携セミナー】
主催:株式会社技術情報協会
講座内容
本講では、日頃皆さまがお使いのExcelを利用し、データ・リテラシーとして必要なデータの理解から分析までを、操作や出力結果の見方を含めて解説致します。単なる座学ではなく、明日からの業務で役立てて頂けるよう「演習」も行います。
習得できる知識
・吸着のメカニズムと等温線の解析法
・ガス吸着法による多孔性材料の特性評価と分離性能への応用~比表面積・細孔分布・吸着量・吸着速度・分配係数~
担当講師
(国研)産業技術総合研究所 材料・化学領域 副領域長 博士(工学) 遠藤 明 氏
マイクロトラック・ベル(株) 営業推進課 マネジャー・統括プロダクトマネジャー(吸着・触媒) 博士(工学) 吉田 将之 氏
セミナープログラム(予定)
【10:30-14:30】※途中、お昼休憩含む
1.吸着のメカニズムと等温線の解析法
(国研)産業技術総合研究所 材料・化学領域 副領域長 博士(工学) 遠藤 明 氏
【習得できる知識】
・吸着等温線の正しい測定法を理解できる。
・吸着等温線の正しい解析法を習得できる。
【講座の趣旨】
吸着現象は、身の回りではシリカゲルによる脱湿や活性炭による脱臭、中空糸を用いた浄水などに、工業的には化学品の高度精製等に幅広く利用されています。また、材料科学の分野では、気体分子をプローブとして吸着等温線を測定・解析することにより固体の細孔構造や表面特性を評価する重要な手法となっています。
本セミナーでは、吸着現象の基礎から吸着等温線の測定方法および解析方法について、解説を行います。正しい測定法、解析法を理解することにより、技術者・研究者の方々がより効率的に気体吸着を利用した材料評価を行うことができるようになることを目指します。
1.はじめに
1.1 吸着現象とは
1.2 吸着等温線とその分類
1.2.1 吸着等温線の形状
1.2.2 吸着ヒステリシス
1.3 吸着等温線の解析からわかること
2.吸着等温線の測定法
2.1 測定方法(容量法、重量法、流通法)
2.2 測定ガスの選択
2.3 測定の流れ
2.3.1 サンプリング
2.3.2 前処理
2.3.3 死容積測定
2.3.4 等温線測定
3.吸着等温線の解析法
3.1 比表面積(BET理論と比表面積の算出)
3.2 比較プロット法
3.3 細孔径分布の解析
【質疑応答】
—————————————————————
【14:45-16:15】
2.ガス吸着法による多孔性材料の特性評価と分離性能への応用~比表面積・細孔分布・吸着量・吸着速度・分配係数~
マイクロトラック・ベル(株) 営業推進課 マネジャー・統括プロダクトマネジャー(吸着・触媒) 博士(工学) 吉田 将之 氏
【略歴】
・化学工学会 分離プロセス部会 吸着・イオン交換分科会 副代表(2023年~)
・日本吸着学会 運営委員(2013年~)分離技術会 運営委員(2021年~)
・ISOTC24SC4WG3委員(比表面積・細孔分布)(2010年~)
【講座の趣旨】
カーボンニュートラルの達成に向け、多孔性材料を用いた二酸化炭の分離・回収に注目が集まっています。本講座では、ゼオライトや活性炭といった多孔性材料を題材に、正確な吸着等温線の測定方法、BET法による比表面積、GCMCおよびDFT法による細孔径分布の解析手法をご紹介します。さらに、バイオガスを想定した各ガス成分の吸着速度評価を活用したガス分離性能の評価について、実際の測定データを基に解説します。
1.吸着等温線測定によりわかること
2.BET比表面積解析法
3.古典的細孔径分布と新規細孔径分布解析法の違い
4.吸着速度評価と解析
5.バイオ模擬ガス(N2、CH4、CO2)分離のための活性炭の構造評価と吸着速度解析による分離性能評価
【質疑応答】
公開セミナーの次回開催予定
開催日
未定
開催場所
未定
受講料
未定
備考
資料は事前に紙で郵送いたします。
お申し込み方法
★下のセミナー参加申込ボタンより、必要事項をご記入の上お申し込みください。
※お申込後はキャンセルできませんのでご注意ください。
※申し込み人数が開催人数に満たない場合など、状況により中止させていただくことがございます。