造粒技術の基礎・装置から前後処理などの実践ノウハウ、スケールアップ参考例まで【提携セミナー】

生産/製造/加工技術 生産技術・品質保証 設備導入・保守 実務スキル
造粒技術の基礎・装置から前後処理などの実践ノウハウ、スケールアップ参考例まで【提携セミナー】
| 開催日時 | 2025/8/22 (金) 10:30-17:00 *途中、お昼休みや小休憩を挟みます。 |
|---|---|
| 担当講師 | 吉原 伊知郎 氏 |
| 開催場所 | 【会場受講】[東京・大井町]きゅりあん 5階第3講習室 |
| 定員 | - |
| 受講費 | 【会場受講】:1名52,800円(税込(消費税10%)、資料付) |
造粒技術の基礎・装置から前後処理などの
実践ノウハウ、スケールアップ参考例まで
≪小型透明デモ機実験を通じて、粉体・粒子の挙動を体感的に理解する≫
【提携セミナー】
主催:株式会社情報機構
〇実務経験豊富な講師が、理論/現場での実際の両面から解説。
〇造粒技術の基礎・様々な装置から、機能性粒子を造るためのバインダー利用や前後処理、事例を交えたスケールアップのポイントおよびトラブル要因と対策まで。
〇各装置を小型透明化したデモ機による実演も随所に登場。挙動を「実際に観る・触る・操作する」ことで実践的なノウハウ・コツを獲得できます。
■はじめに
造粒技術は、機能性材料を造り出す基本的な「粉体処理技術」である。しかしながら、“連続体”である「気体」「液体」とは異なる物性を持つ「粉体」(“離散体”と称する)を扱う分野であるために、極めて特殊な範囲の経験と知識が必要である。
ビッグデータやIoTをうまく利用するにも、その基本的処理技術を把握しておかなければ、AIの記述を正しく判断・利用することができない。本講座は、講師の経験と分析から得られた粉体処理技術の基本から「造粒に関わる分野」を解説し、小型透明モデルの実演から、参加者に体験的な学習を行う。その結果を分析し、それぞれの現場で「利用/応用可能な理解」を与えることを目的としている。
◆受講後、習得できること
- 造粒技術の基本、どの様に粒が造られるかの基本原理
- 機能性粒子を得る造粒を行うための「前処置と後処理」
- 造粒原理の分類と、求める機能を与えるために最も適した造粒原理の把握
- 流れ易い粒、環境によって分解し内容物を放出する粒子、触媒機能を持つ粒子など
- 粉体/粒体であるがための「プロセルトラブル」の原理と分類、対応手法
- トラブル解決のための、コスト低減にかかる手法、実例
など
◆受講対象者
- 粉体/粒体材料の研究開発を始めたばかりの方から、ある程度の研究経験を経た方
- 業務へ活かすため、粉体/粒体処理技術の知見を得たいと考えている方
- 新材料の開発に取り組んでいるが、粉体取り扱いに関する課題があり困っている方
- 造粒の原理選定による、企画した目的機能を与える「処理方法/処理装置」を知りたい方
- 本テーマに興味のある方なら、どなたでも受講可能です
◆必要な予備知識など
- 物理・化学の基礎知識
- 工業専門高校卒業レベルの化学/工学の知識
当日実施する小型透明デモ機の一例(本画像以外のデモ機も多数用います)
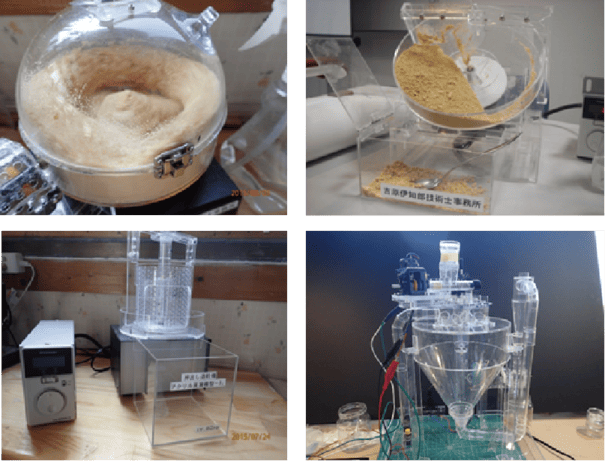
担当講師
吉原伊知郎技術士事務所 所長 吉原 伊知郎 氏
※元奈良機械製作所 取締役
日本粉体工業技術協会 会友
造粒分科会 幹事会技術アドバイザー(元代表幹事)
※希望者は講師との名刺交換が可能です。
■ご略歴など:
1976年東京農工大学工学部 化学工学科卒業
同年株式会社奈良機械製作所 入社
乾燥、粉砕、造粒、表面改質のプロセス開発に関わる
計画設計部長、海外営業部長を経て
1994~2001年奈良機械製作所ヨーロッパ支社支店長 ドイツ駐在
2001年より本社勤務。日本粉体工業技術協会、造粒分科会代表幹事
取締役部長、取締ヨーロッパ支店長を経て2014年フェロー就任
2015年1月より吉原伊知郎技術士事務所開設
技術士(機械部門)、東京農工大学技術士会会長
趣味:機械模型製作、山登り、ジョギング
■本テーマ関連学協会での活動:
・日本粉体工業技術協会 造粒分科会にて、技術討論会主催、2001年4月より2015年3月まで代表幹事。現在 幹事会技術アドバイザー。
・専門誌解説(化学装置誌等)粉体工業展ルポ、初心者のための粉体トラブル講座等
・日本技術士会 技術士協同組合 リスクマネージメント研究会所属。
■関連解説書籍:
「よくわかる粉体・粒体ができるまで 機能を持った粒をつくる造粒技術」(日刊工業新聞社・2022年1月)
セミナープログラム(予定)
1.造粒技術を俯瞰する(粉体取り扱い技術の全体から位置づける)
1)様々な技術分野で用いられている単位操作は、他の業界でも参考になる
2)「流動性の良い粒子」を作るには、どんな造粒原理が向いているか
3)「硬く強い粒子」を生成するには、どんな造粒原理が向いているか
4)「液中崩壊製の良い粒子」はどの造粒原理
5)「フレーバー」を残したい場合は?コストの低い造粒方法は
6)「多孔性粒子」で気体が外面とつながっている粒子の造粒手法は
2.造粒操作の粒子内的現象(攪拌造粒を例に)
1)液体バインダー投入で始まる液架橋現象
2)小さな粒子が取り込まれ、大きな粒子が整粒される
3)重力/遠心力による「転がり運動」により真球性が向上する
4)原料の「ローピングモーション」により、しまった重質の粒子になる
5)表面に液体バインダーを存在させると「コーシング造粒」が発現する
6)表面改質/複合粒子の創成のメカニズムと複合化原理
3.各造粒装置の構造とバリエーション
1)小型透明粉体挙動モデルにて実演、実際に粉を粒にする
(混合造粒機、転動造粒機、流動層造粒機、球形化/表面改質装置)
2)各造粒機の運転パラメーター(噴霧造粒機のクールモデル)
3)物性の異なる粒子を用いた造粒
4)偏析を防止し、混合状態を固定化する造粒
4.バインダーの利用とその目的
1)医薬品で使われるバインダー
2)食品業界で使われるバインダー
3)化学品、金属粒子に使われるバインダー
4)様々なバインダーと造粒方法、造粒手法でできる粒・粒子の特徴
5.前処理と後処理
1)粉砕は前処理として素材の粒径を同一とする手法
2)乾燥は、液体バインダーを投入して造粒した場合の必須後工程
3)乾燥現象を伴う造粒手法は、混相流体取り扱いの基本
4)溶融造粒は真球性粒子を造る、最適な手法(3Dプリンター積層粒子等)
5)熱を加える、熱を取り去る技術を併用して「粒子の品質」を高める
6.スケールアップの例
1)粉体を扱う装置のスケールアップは「現象を理解してその要素を分ける」
2)装置サイズを大きくするのでは無く、現象の規模を大きくする事
3)熱量依存か、物質移動依存か、優先順位の大きい要因は何か
4)各装置固有の操作パラメーターと、その効果が大きい理由
7.粉・粒を扱うプロセスのトラブル要因
1)粉は魔物と言われる所以
2)操作中に物性が著しく変化する粉体プロセスは何か
3)トラブル対策の基本、複雑な現象はシンプルに分解する
4)偏析現象を体感する
8.一般的な粉体取り扱い/造粒操作時のトラブルとその回避方法
1)コスト・パフォーマンスの優れたトラブル対策
2)トラブルの優先順位付け
3)解決策を仕込んでおくが、使わなくても良い場合はそのままで良い
4)同じ化学式、同じ平均粒径、同じ水分値でも油断はできない
9.最近の造粒業界における「造粒操作の連続化」要求事項、そのセンサーとシステムの考え方
・アウトプットできない知識は、本当に理解した知識ではない、といわれる理由を解説
・セミナーでは、参加されたメンバーが、理解されたかどうかの確認をしながら進める
<質疑応答・個別相談・講師との名刺交換>
公開セミナーの次回開催予定
開催日
2025年8月22日(金) 10:30-17:00 *途中、お昼休みや小休憩を挟みます。
開催場所
【会場受講】[東京・大井町]きゅりあん 5階第3講習室
受講料
【会場受講】:1名52,800円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき41,800円
※学校法人割引;学生、教員のご参加は受講料50%割引
●録音・録画行為は固くお断りいたします。
会場(対面)セミナーご受講に関する各種案内(必ずご確認の上、お申込みください。)
●配布資料は、印刷したものを当日会場にてお渡しいたします。
●当日会場でセミナー費用等の現金支払はできません。
●昼食やお飲み物の提供もございませんので、各自ご用意いただけましたら幸いです。
●録音・撮影行為は固くお断りいたします。
●講義中の携帯電話・スマートフォンでの通話や音を発する操作はご遠慮ください。
●講義中のパソコン使用は、講義の支障や他の方のご迷惑となる場合がありますので、極力お控えください。場合により、使用をお断りすることがございますので、予めご了承ください(パソコン実習講座を除きます。)
お申し込み方法
★下のセミナー参加申込ボタンより、必要事項をご記入の上お申し込みください。















































