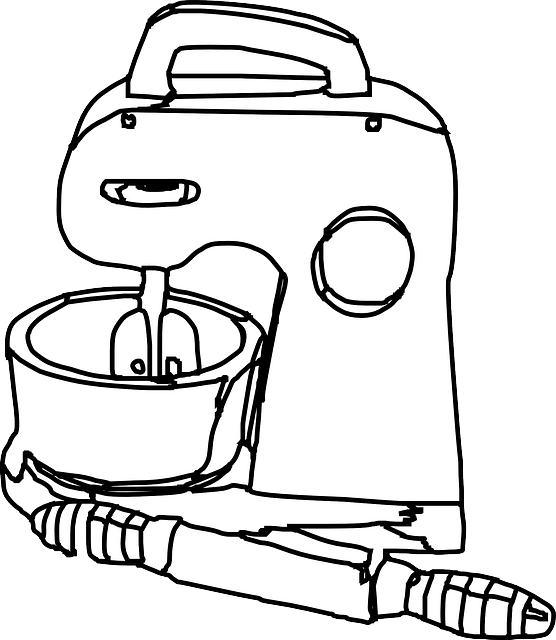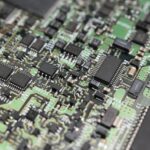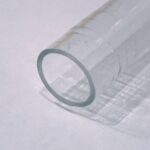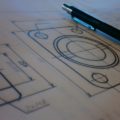撹拌操作・スケールアップの基礎とトラブル対策【名古屋開催】【提携セミナー】

生産/製造/加工技術 生産技術・品質保証 設備導入・保守 実務スキル
撹拌操作・スケールアップの基礎とトラブル対策【名古屋開催】【提携セミナー】
おすすめのセミナー情報
もっと見る| 開催日時 | 2024/10/7(月) 10:00~15:30 |
|---|---|
| 担当講師 | 加藤 禎人 氏 |
| 開催場所 | 【会場受講】【名古屋開催】名古屋市中小企業振興会館(吹上ホール) 4F 会議室4 |
| 定員 | 20名 ※満席になり次第、募集を終了させていただきます。 |
| 受講費 | 非会員: 55,000円 (本体価格:50,000円) 会員: 49,500円 (本体価格:45,000円) |
★攪拌についての可視化画像や実験例を中心にした分かりやすい説明から、
ラボ見学でさらに理解を深められます!
撹拌操作・スケールアップの基礎とトラブル対策
【名古屋開催】
《名古屋工業大学・ラボ見学付き》
【提携セミナー】
主催:株式会社R&D支援センター
撹拌の基礎から応用までを多くの可視化画像や実験例を中心に解説し、とくに、撹拌所要動力は撹拌を理解する上で最も基本となる事柄なので、古くから用いられてきている手法だけでなく、その欠点を克服した応用範囲の広い動力の推算方法を詳細に解説します。また、異相系の撹拌や最近の技術開発動向についても解説します。
◆ 習得できる知識
- 撹拌槽の設計や装置改造に関する知識
- 高粘度流体撹拌と低粘度流体撹拌の違い
- 種々の撹拌槽形状の撹拌所要動力の推算方法
- 撹拌槽の性能評価の方法
- 撹拌槽スケールアップの知識
担当講師
名古屋工業大学 工学部 生命・応用化学科 教授 博士(工学) 加藤 禎人 氏
<ご専門>撹拌・混合
<学協会>化学工学会(平成26,27年度 粒子・流体プロセス部会ミキシング技術分科会 会長)
セミナープログラム(予定)
1.撹拌の基礎
1-1.撹拌翼の構成
1-2.撹拌翼の種類
1-3.撹拌操作に必要な主な無次元数
2.撹拌の基本的な特性
2-1.流動特性:どのような場合に固体的回転部やドーナツ状の混合不良部が発生するのか?
2-2.動力特性:層流での動力数、乱流での邪魔板の有無による動力数の変化
2-3.混合特性:層流および乱流での無次元混合時間の特性
2-4.伝熱特性:伝熱係数に対する通常の相関式と動力を用いる方法
3.異相系の撹拌
3-1.気液系の撹拌:なぜ通気時は動力が低下するのか?
3-2.固液系の撹拌:固体粒子分散に必要最小限の翼回転数とは?
3-3.液液系の撹拌:液滴の細分化はどのようにして行われるのか?
4.新型撹拌翼(大型翼)の開発経緯
4-1.フローパターンや混合状態の最適化を基にして各種の撹拌翼が開発された経緯を説明
4-2.2枚パドル翼が混合に有利な理由。
5.撹拌所要動力
5-1.なぜ、撹拌所要動力が重要なのか?
5-2.永田の式および永田の式の弱点を克服する新しい相関式
5-3.幅広い邪魔板条件での相関式
5-4.演習:例題を用いて動力を関数電卓で計算する。
5-5.計算された動力の妥当性を検証する方法
6.トピックス
6-1.層流混合に画期的なヒントをもたらす流脈の理論
6-2.流脈を用いた大型翼の性能比較
6-3.流脈を用いた新型撹拌翼の開発
6-4.新型ホームベース翼の開発とその性能
6-5.ホームベース翼を用いたスケールアップ
スケジュール
10:00~11:45 講義
11:45~12:30 昼食
12:30~14:00 講義
14:00~14:10 休憩
14:10~15:30 講義
15:30~16:00 休憩・移動
16:00~17:00 名古屋工業大学 ラボ見学
※状況により多少変更する可能性があります。
公開セミナーの次回開催予定
開催日
2024年10月07日(月) 10:00~15:30
開催場所
【会場受講】【名古屋開催】名古屋市中小企業振興会館(吹上ホール) 4F 会議室4
受講料
非会員: 55,000円 (本体価格:50,000円)
会員: 49,500円 (本体価格:45,000円)
■会員(案内)登録していただいた場合、通常1名様申込で55,000円(税込)から
- 1名で申込の場合、49,500円(税込)へ割引になります。
- 2名以上同時申込で参加者全員が会員登録をされた場合、1名につき33,000円(税込)になります。
※セミナー主催者の会員登録をご希望の方は、申込みフォームのメッセージ本文欄に「R&D支援センター会員登録希望」と記載してください。ご登録いただくと、今回のお申込みから会員受講料が適用されます。
※R&D支援センターの会員登録とは?
ご登録いただきますと、セミナーや書籍などの商品をご案内させていただきます。
すべて無料で年会費・更新料・登録費は一切かかりません。
備考
昼食・資料付
特典
[ラボ見学付]
※以下の装置等の操作環境をご覧いただけます。(実験室内の写真撮影も可能です。)
- 撹拌所要動力測定装置
- 種々の撹拌翼(マックスブレンド、フルゾーン、MR205、HB翼、AM翼など多数)
- レーザー光による流脈可視化実験装置
持参物
関数電卓(講義中の演習で使用します)
※スマートフォンの電卓アプリでも問題ございません。横画面にして関数機能が使用できることを確認して下さい。
お申し込み方法
★下のセミナー参加申込ボタンより、必要事項をご記入の上お申し込みください。