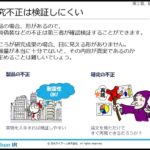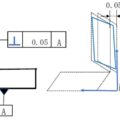3分でわかる技術の超キホン 「モデル生物」とは?代表的なモデル生物の特徴・利点・研究例などを一挙紹介!
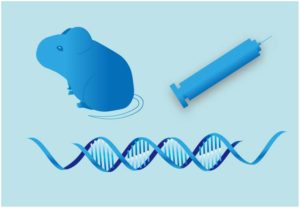
医薬品の開発には、マウスなどの動物が用いられていることはよく知られています。
医薬品以外にも、遺伝子の研究や生命現象の研究等に用いられる生物は、いろいろな種類の動物・生物が知られておりますが、多くの研究者によって同じ生物が用いられることがあります。
これらを「モデル生物」といい、研究者はモデル生物を用いることによって多くのメリットを得ることができます。
今回は、その「モデル生物」について焦点を当ててみました。
目次
モデル生物の条件・メリット
実験に用いられる生物はどのようなものでもよいというわけではなく、モデル生物として使われる条件を兼ね備える必要があります。主なものとして以下のものが挙げられます。
- サイズ等が扱いやすい
- 観察しやすい
- 入手、維持しやすい(安定して買える・安い・飼育しやすい)
- 世代交代が早い
- ゲノムサイズが小さい、またはゲノムが解明されている
- 遺伝子組み換えができる
例えば、大腸菌は世代交代が最短で20分と短く、寒天培地で同一の遺伝子を持った株が簡単にたくさん手に入ります。遺伝子組み換え技術が実用化されたのも大腸菌があったからこそであり、現在も大腸菌なしには分子生物学の実験は進まないとされています。
また、ショウジョウバエは、1日に約50個産卵、10日ほどで成虫になり、飼育が安価で容易であり、さまざまな変異体を作り出して安定に維持できるなど、実験を容易にする便利な特徴を備えていることから、生物学の研究によく用いられています。
大腸菌やショウジョウバエは今でも世界中の研究者が利用しており、多くの研究者が同じモデル生物を扱うことで、研究の結果や種々データ、知識等を蓄積・共有できるため、効率よく研究を進めることができる利点もあります。
代表的なモデル生物の種類としては、単細胞生物では大腸菌、酵母、多細胞生物ではショウジョウバエ、線虫、ゼブラフィッシュ、マウス、植物ではシロイヌナズナなどが挙げられます。
以下に代表的なモデル生物を取り上げてみます。
モデル生物の例① 大腸菌
腸内細菌の一種である大腸菌は、1940年代のはじめに発見され、それ以来この菌は遺伝学の研究対象とされるようになりました。
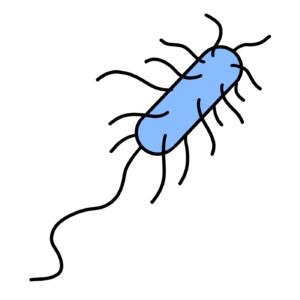
大腸菌は、世代交代が最短で20分と短く、寒天培地で培養することにより、同一の遺伝子を持った株が無数に手に入ることなどから、モデル生物の代表として扱われています。
遺伝子組み換え技術が実用化されたのも大腸菌の研究によるもので、現在も大腸菌なしには分子生物学の研究は考えられないといえます。
また、大腸菌は好気条件でも嫌気条件でも生育でき、細胞分裂により増殖します。
有性生殖により、雄菌から雌菌に遺伝子が移行して組換えが起きます。
大腸菌は巨大な環状二本鎖DNA(染色体DNA)を持っており、1997年この染色体DNAの全長460万塩基対の配列がすべて解読され、4288個のタンパク質をコードする遺伝子があることが明らかにされました。
大腸菌を用いた研究例
- 遺伝子組み換え技術の実用化。
- DNAの複製、RNA合成、タンパク質合成など、分子生物学の主要な知見は主として大腸菌を用いた研究により得られました。
- 生体物質の分解経路や合成経路などの生化学の知見も大腸菌を用いた研究で得られたものが多いとされています。
- 大腸菌は組換えDNAの宿主としても有用であり、遺伝子操作実験には欠かせない存在となっています。
モデル生物の例② ショウジョウバエ
線形動物門に属するハエ目(双翅目)ショウジョウバエ科に属するハエの一種であるキイロショウジョウバエが研究によく用いられています。
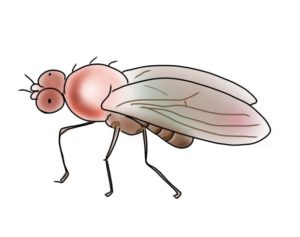
ショウジョウバエは世代交代が早く、その産卵数は1日に約50個で、10日ほどで成虫になり、また、体長が小さい為試験管でも飼育が可能です。
1910年にアメリカの遺伝学者Morganは、白眼およびその他の突然変異体を用いた研究から、遺伝学の基礎となる多くの重要なこと、例えば染色体地図を明らかにしました。
この功績によってMorganは1933年にノーベル賞を受賞しています。
その後、ショウジョウバエはエックス線照射で突然変異を起こせるようになり、ゲノムが解読され、遺伝子導入の技術も確立し、ショウジョウバエの重要性は非常に高くなっています。
ショウジョウバエを用いた研究例
- 神経幹細胞のマーカー「MUSASHI」を発見。
- 形態形成遺伝子群が多細胞生物の体作りにおいて共通の働きを持つことを発見。
- ショウジョウバエにおいて、気管上皮細胞内の逆行性小胞輸送システムが気管の長さを制御していることを明らかにした。
- キイロショウジョウバエを用いて概日時計(一日[24時間]を測る体内時計)と温度適応についての研究。
- 組織において適応度の異なる2種類の細胞が近接すると、適応度のより高い細胞が生き残り、より低い細胞が排除される「細胞競合」という現象をショウジョウバエの翅原基において発見。
- ショウジョウバエの脳の性別を決める分子の仕組みを解明。
- ショウジョウバエでの研究成果で”女性脳”と”男性脳”を切り替えるスイッチ遺伝子を発見。
- ハエの音識別学習の発見と神経機構の解明。
- わずかなリズムの違いを聞き分ける脳のしくみを発見。
- 神経変性疾患(脳の神経細胞が徐々に死んでいく病気、アルツハイマー病など)の研究においてはショウジョウバエを用いた実験が広く研究に用いられている。
モデル生物の例③ シロイヌナズナ
アブラナ科の植物で、ユーラシア大陸で広く自生しています。ぺんぺん草の仲間です。

シロイヌナズナは、世代時間(個体が成長して種を収穫するまで)が6週間と短く、塩基の数が種子植物の中で最も少なく、染色体の数も5対と少ないという特徴があり、ゲノムが小さいことから、高等植物の中で最初にゲノム解読がされています。
シロイヌナズナに関する種々の情報も豊富で、モデル生物としての条件を有しています。
シロイヌナズナを用いた研究例
- 植物の根を分岐させる「側根」を作り出す細胞(側根創始細胞)が、すぐ近くに生じないように働くペプチドTOLS2(トルス2)を、モデル植物シロイヌナズナから発見した。
- 外部から投与することで植物の塩ストレス耐性を強化できるペプチドを発見。
- 花粉管誘引物質LUREペプチド群の発見。
- 他種の花粉、排除する遺伝子をシロイヌナズナで発見。
- 健全な植物体から、病原微生物に対する免疫反応を抑制する因子(内因性サプレッサー;endogenous suppressor)を分離・精製することに世界で初めて成功。
- 植物細胞の “形を決める” 遺伝子を発見。
- 植物の根が水を求めて伸びるために必須な細胞を発見。
- 植物の光化学オキシダント耐性遺伝子OZS1の発見。
- 植物の双葉を2枚にする酵素を発見。
モデル生物の例④ 酵母
実験酵母の代表としては、出芽酵母と分裂酵母があり、ともに全遺伝子の塩基配列が明らかにされています。
酵母のモデル生物として優れた点としては、約2時間に1回分裂し、培養や保存が容易、経済的で、病原性がなく、外部SNAを効率よく形質転換します。
さらに、単細胞生物ではあるものの、真核生物の基本的な細胞機能を有していることなどから、多くの生命現象の解明において利用されています。
大腸菌は原核細胞のモデルとして、酵母は真核細胞のモデルとしてしばしば用いられます。
酵母は、遺伝子機能解析が最も進んでおり、変異体などの研究材料と機能情報が充実しているモデル生物といわれています。
酵母を用いた研究例
- 酵母細胞を用いた研究からの「オートファジー(細胞内分解機構)の仕組みの解明」(※大隅先生がノーベル生理学・医学賞を受賞)
- 発酵食品分野は多数
モデル生物の例⑤ マウス
マウスは、ヒトのモデルとして扱われる生物の代表とされています。

マウスは、ヒトと同じ哺乳類に属し、多くの系統、変異体が確立されています。
飼育スペースが小さく、多産であることなどからモデル生物としての特徴を兼ね備えています。
ヒトの遺伝子のうちおよそ99%がマウスと同じで、遺伝子の発現にも大きく影響を及ぼす染色体上の並び順までもヒトとマウスの間でほとんど同じであることが明らかにされています。
ヒトの病気が遺伝子によるものであると考えられる場合、その可能性を調べる方法として、マウスに同様の遺伝子変化を起こさせ、マウスにヒトと同じような症状が出るかを見ることができ、実際に多くの遺伝子変異マウスがヒトの疾患と同様の症状を示すことから、ヒト疾患モデル動物として研究されています。
また、疾患モデルマウス(※)は、新薬の開発など薬の研究にも用いられています。
※疾患モデルマウスとは?
心肥大、心不全等の心臓疾患をはじめ、循環器疾患、腎疾患、肺炎、自己免疫疾患、眼疾患、糖尿病、血液疾患、メタボリックシンドローム(肥満・糖尿病)、免疫疾患、生活習慣病・筋萎縮(ミトコンドリア筋症)、発癌等々・・多くの疾患モデルマウスが報告されており、これらを用いた動物試験は、新薬候補物質のヒトでの安全性および有効性を予測するために非常に重要なものとなっています。
モデル生物の例⑥ アフリカツメガエル
アフリカツメガエルは、アフリカ中南部を原産とする無尾目ピパ科ツメガエル属に分類されるカエルで、湖沼などの止水に生息しています。低温耐性があり、凍結しなければ無加温で越冬可能です。

【アフリカツメガエル】
アフリカツメガエルは、養殖により、実験材料、また教材として容易に手に入れることができるようになっています。
アフリカツメガエルを用いる利点としては、下記が挙げられます。
- ホルモン注射及び体外受精により一年中季節によらず大量の受精卵(数千個)を得ることができる。
- 胚そのものが大きいため発生の様子を観察しやすい。
- 詳細な発生ステージ表が作成されている。
- 一生を水中で過ごすので飼育しやすい。(水槽で飼育可能)
- 生き餌を与える必要がない 固形飼料で飼育することができる。
- 至適生育温度範囲が広い。
- 均一な遺伝子組成を持つ集団が作られている。
アフリカツメガエルは、動物の発生・分化の問題に取り組む世界中の研究室で広く用いられています。
また、四肢の形成・再生やアポトーシス(プログラム細胞死)の研究にも役立ってきました。
アフリカツメガエルを用いた研究例
- ジョン・ガードン博士(山中伸弥博士と共にノーベル生理学・医学賞を受賞)はこのカエルを用いて、「細胞の初期化」を初めて実験的に示した。
- 油井宇宙飛行士によってアフリカツメガエルの細胞が国際宇宙ステーションに運ばれ、「きぼう」内での「無重力ストレスの化学的シグナルへの変換機構の解明(Cell Mechanosensing)」実験に用いられた。
- アフリカツメガエルの皮膚から「マガイニン」と呼ばれる抗菌性のペプチドが発見。
最近は、性的成熟に四~五ヶ月しか要せず、かつ、ゲノム解析もほぼ終了している近縁種(Siurana tropicalis)が使用され始めているようです。
なお、アフリカツメガエルが日本国内の湖沼等で大繁殖している問題が報告されており、生態系への影響が懸念されています。
モデル生物の例⑦ イベリアトゲイモリ
両生類のイモリは、心臓や脳をも再生することができるという非常に高い再生能力を持っていることで知られ、古くから再生医学や発生生物学における重要な実験動物として研究されてきました。
中でも、飼育や繁殖が容易なイベリアトゲイモリ(Pleurodeles waltl)は、新しいモデル生物として注目されています。
イベリアトゲイモリは、主にイベリア半島に生息する比較的大型の有尾両生類で、モデル動物としては、餌付けがしやすいうえに成長が早く、実験室内の環境でも飼育が容易で、一年程度で子孫が得られ、通年受精卵を得ることができるというメリットがあります。
2012年に核移植とクローンの研究でノーベル賞を受賞したガードン博士も、このイモリの卵や体細胞を用いて転写のリプログラミング研究を行っていました。
再生医療や発生生物学の他にも、癌研究、幹細胞生物学、生殖生物学、進化学、毒性学などの研究分野でイモリを活用した研究が大きく発展することが期待されています。
その他のモデル生物
上記の例以外にも、犬、サル、魚なども用いられています。
さらに、新たなモデル生物の候補として、カブトムシ、アブラムシ、ナミテントウなどが検討・開発されています。
以上、いろいろなモデル生物をご紹介させていただきましたが、人類の科学は多くのモデル生物の犠牲の上に成り立っています。
動物実験を行う方は、実験動物についての国際原則である3R(※)を尊重されて実験を行っておられることと思いますが、それ以外の方々も命をささげてくれたモデル生物への感謝の気持ちを忘れないようにしたいものです。
(※)実験動物についての国際原則”3R”とは?
- Replacement(代替): なるべき意識や感覚のない生物に切り替える
- Reduction(削減): 使う数を減らす
- Refinement(改善): 動物が苦しまないよう環境をよりよくする
モデル生物に関する特許調査・文献調査をしてみると?
J-PlatPatでモデル生物に関する特許を調べてみました。
(※いずれも2020年3月時点における検索結果です。)
(1)キーワードによる特許検索
- 論理式: [モデル動物/TX+モデル生物/TX+実験動物/TX+実験生物/TX] ⇒ 43692件
- 論理式: [モデル動物/CL+モデル生物/CL+実験動物/CL+実験生物/CL] ⇒ 1469件
請求範囲およびマウスに限定してみると・・
- 論理式: [モデル動物/CL+モデル生物/CL+実験動物/CL+実験生物/CL]*[マウス/CL] ⇒ 397件
となり、この397件の特許の内容としては、モデル動物の作製方法や医薬品のスクリーニングの特許が多くみられました。
しかし、マウス以外のモデル生物ではヒットする件数が極端に少ない結果となりました。
- [モデル動物/CL+モデル生物/CL+実験動物/CL+実験生物/CL]*[大腸菌/CL] ⇒ 7件
- [モデル動物/CL+モデル生物/CL+実験動物/CL+実験生物/CL]*[シヨウジヨウバエ/CL] ⇒ 6件
- [モデル動物/CL+モデル生物/CL+実験動物/CL+実験生物/CL]*[シロイヌナズナ/CL] ⇒ 1件
- [モデル動物/CL+モデル生物/CL+実験動物/CL+実験生物/CL]*[酵母/CL] ⇒ 9件
- [モデル動物/CL+モデル生物/CL+実験動物/CL+実験生物/CL]*[アフリカツメガル/CL] ⇒ 0件
(2)特許分類(FI)による検索
上記の論理式: [モデル動物/CL+モデル生物/CL+実験動物/CL+実験生物/CL] ⇒ 1469件
の分類コード(FI)ランキングを見てみると、次のようになりました。
| 順位 | 件数 | FI | 説明 |
| 1 | 705/1469 | G01N33 | グループG01N1/00~G01N31/00に包含されない、特有な方法による材料の調査または分析 |
| 2 | 622/1469 | A01K67 | 他に分類されない動物の飼育または繁殖;新規な動物 |
| 3 | 565/1469 | C12N15 | 突然変異または遺伝子工学;遺伝子工学に関するDNAまたはRNA、ベクター、例.プラスミド、・・ |
| 4 | 413/1469 | C12Q1 | 酵素、核酸または微生物を含む測定または試験方法(状態の測定・・ |
| 5 | 294/1469 | C12N5 | ヒト、動物または植物の細胞、例.セルライン;組織;その培養または維持・・ |
| 6 | 259/1469 | A61K45 | A61K31/00~A61K41/00に属さない活性成分を含有する医薬品製剤 |
| 7 | 198/1469 | A61K31 | 有機活性成分を含有する医薬品製剤 |
これらから、「動物」「遺伝子」「医薬品」に関連する特許が多いことが予想されます。
1位のFIがG01N33の705件をざっと見てみると、やはり「動物の作製方法」に関する特許が圧倒的に多くヒットしていました。また、7位のA61K31には、医薬品やそのスクリーニング方法の特許が多くみられました。
(3) Fタームによる特許検索
J-PlatPatの特許・実用新案分類照会(PMGS)で「実験動物」でキーワード検索をしてみますと、以下のFタームが見つかりました。
- 2B101AA11: 実験用動物
- 2B102AA13: 実験動物
- 2B101FA00: 実験動物の飼育装置
このFタームを用いて「実験動物」を検索してみると、以下の件数となりました。
- 論理式: [2B101AA11/FT+2B102AA13/FT] ⇒ 1055件
発明の名称(タイトル)として、「飼育装置」「ケージ」「〇〇器具」「〇〇処理材」などが多くみられました。
文献の調査
次に、J-stageを使って特許以外も含めた文献を検索してみました。
- 検索式:標題: モデル動物 OR標題: モデル生物 ⇒308件
この308件の中には、「自然発症てんかんモデル動物」「モデル生物:マウスを用いたゲノムDNA解析」「創薬研究のための疾患モデル動物」「病態モデル動物の活用」等々の文献がヒットしました。
上記の特許公報や文献の内容についてご興味がある方は、是非ご自身で検索して確認してみてください。
(日本アイアール株式会社 特許調査部 S・T)
☆バイオ・医薬関連技術の特許調査・文献調査は日本アイアールまでお気軽にお問い合わせください。





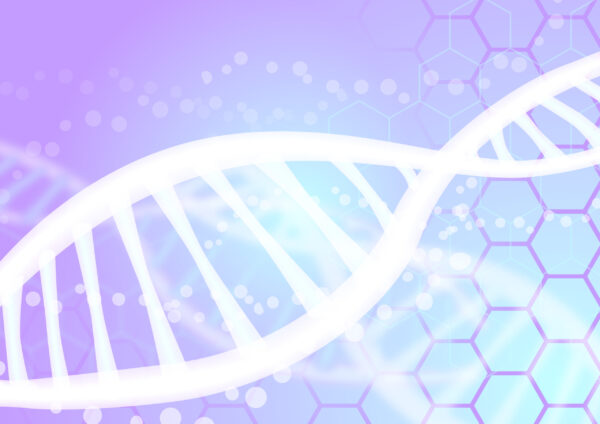
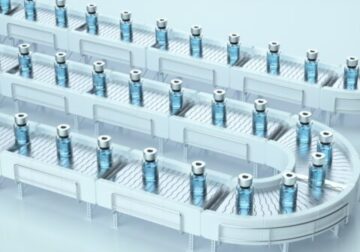








](https://engineer-education.com/wp/wp-content/uploads/2021/08/Experimental-design_0-150x150.jpg)