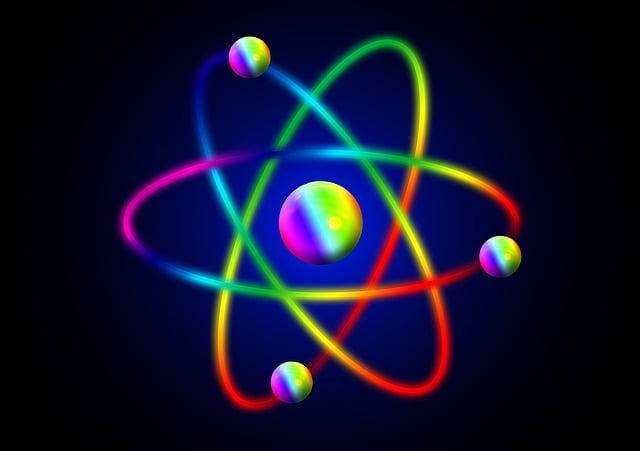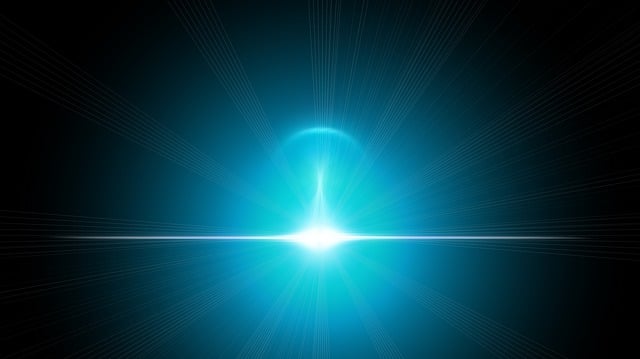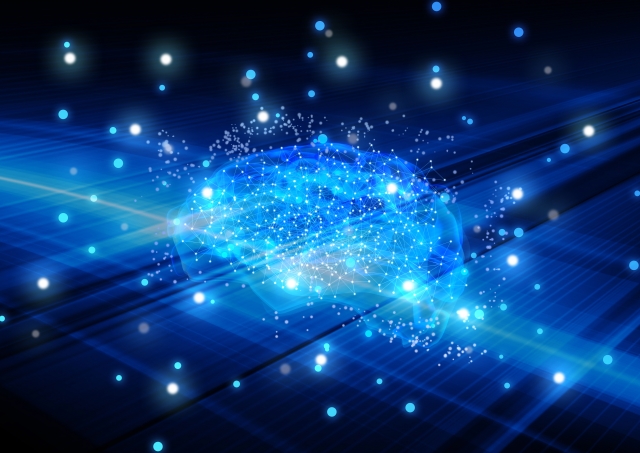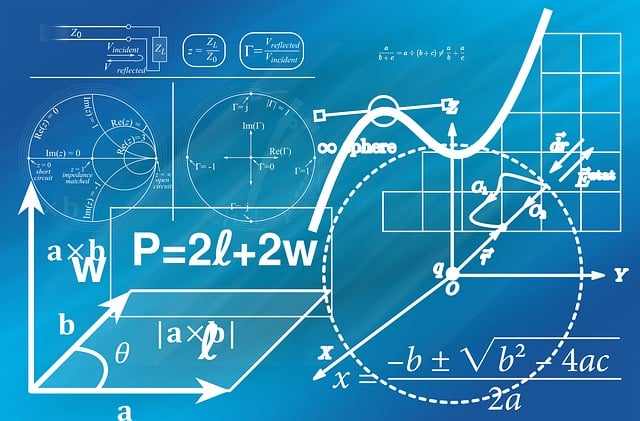原子団寄与法の考え方と利用事例【提携セミナー】
| 開催日時 | 未定 |
|---|---|
| 担当講師 | 船津 公人 氏 |
| 開催場所 | 未定 |
| 定員 | 未定 |
| 受講費 | 未定 |
★マテリアルズインフォマティクスで使える物性データの形式に整えるために!
原子団寄与法の考え方と利用事例
【提携セミナー】
主催:株式会社技術情報協会
講座内容
原子団寄与法は昔から構造活性(物性)相関モデルを構築する手法として用いられてきている。その簡便な概念とともに、原子団という明示的な構造特徴を説明変数として用いていることから、モデルの解釈性という点でもメリットが大きい。このモデルを用いた逆解析を行うことで、得られる原子団集合から構造を組立てることで、目的活性(物性)を有すると考えられる候補構造生成にもメリットがある。ただし、用いる原子団のサイズを適切に決めなければ目的活性(物性)を適切に説明できるモデルとはならないし、モデルの誤差も生じやすい。この講座ではこうした原子団寄与法の考え方とメリット、そして限界を事例とともに理解を深める。
【習得できる知識】
- 原子団寄与法の考え方
- 原子団設定の考え方
- 原子団寄与法を用いた候補構造生成法
担当講師
奈良先端科学技術大学院大学 データ駆動型サイエンス創造センター センター長 特任教授 理学博士 船津 公人 氏
セミナープログラム(予定)
1.原子団寄与法の考え方
2.原子団設定の考え方
2.1 原子団が大きい場合、小さい場合
2.2 原子団間の重なりを許す場合、許さない場合
3.原子団寄与法を用いるメリット
4.原子団寄与法を用いた構造生成
5.原子団寄与法の限界と解決法
6.構造物性相関モデルの実例
6.1 二酸化炭素吸収剤・アルカノールアミンの候補構造生成
6.2 原子団寄与法を用いたモデリングのデモンストレーション
【質疑応答】
公開セミナーの次回開催予定
開催日
未定
開催場所
未定
受講料
未定
備考
資料は事前に紙で郵送いたします。
お申し込み方法
★下のセミナー参加申込ボタンより、必要事項をご記入の上お申し込みください。
★【LIVE配信】、【アーカイブ配信】のどちらかご希望される受講形態をメッセージ欄に明記してください。
※お申込後はキャンセルできませんのでご注意ください。
※申し込み人数が開催人数に満たない場合など、状況により中止させていただくことがございます。