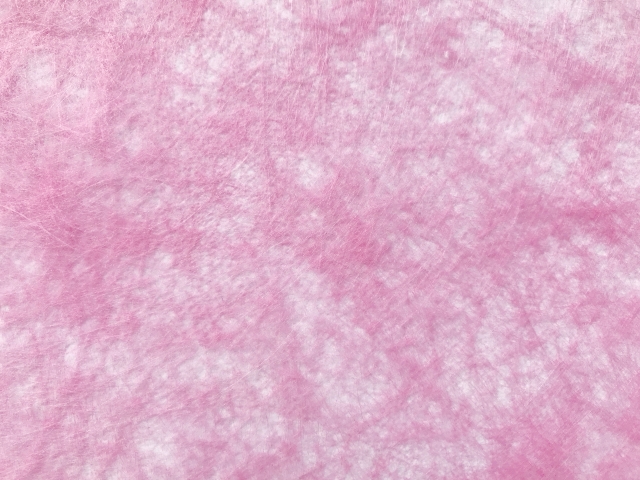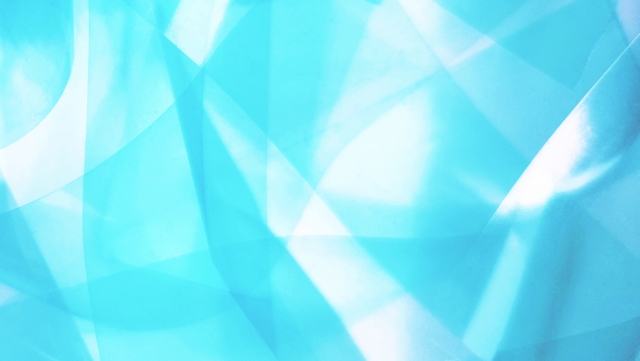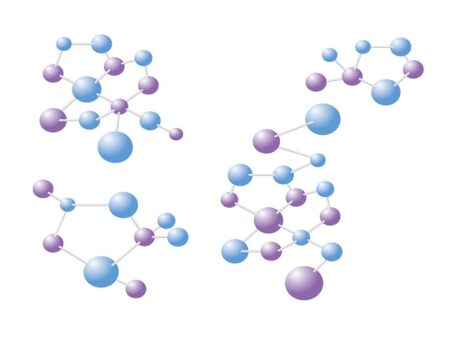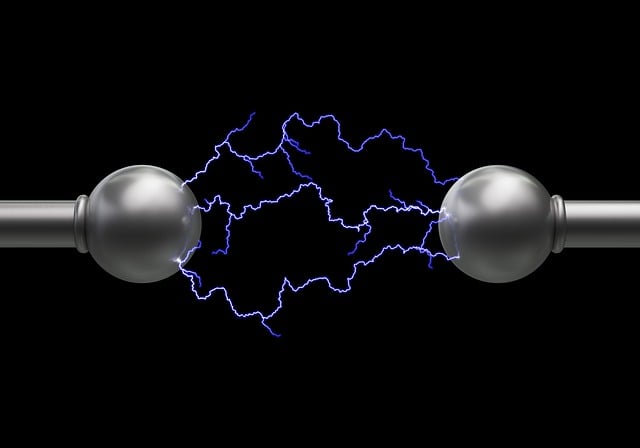ポリプロピレンの基礎知識と活用のポイント【提携セミナー】
| 開催日時 | 2025/9/22 (月) 10:30-16:30 *途中、お昼休みや小休憩を挟みます。 |
|---|---|
| 担当講師 | 小林 豊 氏 |
| 開催場所 | Zoomによるオンラインセミナー |
| 定員 | - |
| 受講費 | 50,600円(税込(消費税10%)、資料付) |
ポリプロピレンの基礎知識と活用のポイント
≪特徴・構造およびその制御・用途展開に向けた加工・設計指針≫
【提携セミナー】
主催:株式会社情報機構
★ポリプロプレンを取り扱う上で役立つ様々な技術的知識について、その要点を押さえ解説します。
◆セミナーポイント
ポリプロピレンは、身の回りで多く使われている汎用樹脂の一つです。その理由として、成形加工しやすい、コストパフォーマンスに優れる、耐久性に優れる上に様々な特性や性能をカスタマイズできる等があげられます。
しかし、その特徴・性能を活かすためには、基本的な構造・物性を把握した上で適切な銘柄を調達し、最適な加工を施す必要があります。
この講座では、ポリプロピレンの持つ特徴を、種々の素材と比較し説明します。その上で、様々な用途展開に向けポリプロピレンを最適に活用するため、非常に幅広い知識の中で、必要となる事柄を広く浅く、基礎から応用までの技術をその要点をふまえ解説していきます。
実務でポリプロピレンを扱っていて、日ごろ疑問を持っている技術者との質疑応答を通して、一方通行では説明されないようなトビックスまで幅広く解説します
◆受講後、習得できること
- ポリプロピレンを選択するにあたり、必要な性能により最適なものを決定できる。
- ポリプロピレンを成形するにあたり、最適な成形条件が設定できる。
- ポリプロピンの部品を設計するにあたり、注意するべきことが分かる。
など
◆受講対象者
ポリプロピレンを取り扱っている技術者は全て対象です。化学企業でポリマーブレンドに使用している方、成形加工会社で成形加工している方、最終製品のために設計している方などです。
担当講師
山形大学 グリーンマテリアル成形加工研究センター 産学連携教授 博士(理学) 小林 豊 氏
*ご略歴:
1985年 出光興産入社 ポリプロピレン系ポリマーブレンドの開発に従事
2021年 同社を定年退職
同年 山形大学 産学連携教授 海洋分解性高分子の開発に従事
*ご専門および得意な分野・研究:
自動車用途向けのポリプロピレン系ポリマーブレンド
海洋分解性高分子のポリマーブレンド
射出成形
*本テーマ関連のご活動:
Society of Plastics Engineers 日本支部 理事
セミナープログラム(予定)
1. ポリプロピレンの歴史
1.1 おいたち
1.2 樹脂改良の足跡
1.2.1 低温における衝撃強度の改良
1.2.2 剛性の改良
1.2.3 透明性の改良
1.2.4 難燃化
1.2.5 耐候性の改良
1.2.6 耐銅害性グレード
1.2.7 帯電防止
1.2.8 二次加工性の改良
1.2.9 染色性の改良
2. ポリプロピレンの化学
2.1 プロピレン
2.2 プロピレンの重合
2.2.1 重合触媒
2.2.2 重合反応
2.3 ポリプロピレンの製造法
2.3.1 ホモポリマー
2.3.2 ランダム共重合体
2.3.3 衝撃グレード
3. ポリプロピレンの構造と物性
3.1 分子量と分子量分布
3.1.1 分子量
3.1.2 分子量分布
3.2 分子構造と結晶構造
3.2.1 一次構造
3.2.2 立体規則性
3.2.3 二次構造
3.2.4 高次構造
3.3 熱的性質
3.3.1 ガラス転移温度と融解温度
3.3.2 PVT
3.3.3 緩和
3.3.4 結晶化速度と結晶化度
3.4 溶融物性
3.4.1 メルトマスフローレート
3.4.2 溶融粘度の測定
3.4.3 密度と表面エネルギー
3.5 固体物性・機械的性質
3.5.1 降伏強度,伸び
3.5.2 弾性率
3.5.3 衝撃強度
3.5.4 表面硬度
3.5.5 摩耗抵抗、スクラッチ性
3.6 耐久性
3.6.1 耐クリープ性
3.6.2 耐疲労性
3.7 その他性質
3.7.1 ヒンジ特性
3.7.2 比熱、熱伝導率
3.7.3 電気的性質
3.7.4 耐薬品性、耐ストレスクラッキング性
4. ポリプロピレンの劣化と機能化
4.1 劣化の全体像
4.1.1 外的な要因
4.1.2 内的な要因
4.2 ポリプロピレンの劣化機構
4.2.1 自動酸化反応
4.2.2 β切断による分子量の低下
4.2.3 劣化による構造物性の変化
4.3 安定性を付与する添加剤
4.3.1 酸化防止剤
4.3.2 光安定剤
4.3.3 中和剤
4.3.4 分散剤
4.3.2 架橋剤、分解剤、発泡剤
4.3.3 難燃剤
4.4 機能を付与する添加剤
4.4.1 造核剤
4.4.2 帯電防止剤
4.4.3 滑剤
4.4.4 防曇剤
4.4.5 離型剤
4.4.6 アンチブロッキング剤
4.4.7 抗菌剤
4.4.8 蛍光増白剤
4.5 分析法、試験法
4.5.1 前準備
4.5.2 定性分析
4.5.3 定量分析
5 調色とコンパウンド
5.1 調色
5.1.1 色材
5.1.2 凝集と分散
5.1.3 工業的な混合方法
5.2 コンパウンド
5.2.1 二軸押出機
5.2.2 フィラー充填
5.2.3 ガラス強化
5.2.4 エラストマー変性
5.2.5 反応混練
6. ポリプロピレンの加工法
6.1 延伸加工
6.1.1 無配向と延伸による構造形成
6.1.2 キャストフィルム
6.1.3 BOPP
6.1.4 インフレーションフィルム
6.1.5 溶融紡糸
6.1.6 延伸テープ
6.2 射出成形
6.2.1 射出成形品の構造形成
6.2.2 構造と物性
6.3 その他
6.3.1 中空成形
6.3.2 不織布
6.3.3 シート成形
6.3.4 回転成形
7. ポリプロピレンの用途
7.1ポリプロピレンの性質
7.1.1 ポリプロピレンのプラスチックの中における位置
7.1.2 他樹脂との比較
7.1.3 カタログ、使用銘柄の選定
7.1.4 グレード群毎の成形性
7.2 使用例
7.2.1 家庭用品
7.2.2 電気産業関係
7.2.3 自動車関係部門
7.2.4 化学工業用
7.2.5 包装,輸送用資材
7.2.6 建材
7.2.7 農、畜、水産業用資材
7.2.8 衣料
7.2.9 医療用
7.2.10その他の用途
<質疑応答>
公開セミナーの次回開催予定
開催日
2025年9月22日(月) 10:30-16:30 *途中、お昼休みや小休憩を挟みます。
開催場所
Zoomによるオンラインセミナー
受講料
【オンライン受講】:1名50,600円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき39,600円
*学校法人割引;学生、教員のご参加は受講料50%割引。
●録音・撮影行為は固くお断り致します。
備考
●配布資料は、印刷物を郵送で1部送付いたします。
- お申込みの際にお受け取り可能な住所を必ずご記入ください。
- 郵送の都合上、お申込みは4営業日前までを推奨します。(土、日、祝日は営業日としてカウントしません。)
- それ以降でもお申込みはお受けしておりますが(開催1営業日前の12:00まで)、その場合、テキスト到着がセミナー後になる可能性がございます。ご了承の上お申込みください。
- 資料未達の場合などを除き、資料の再配布はご対応できかねますのでご了承ください。
●当日、可能な範囲でご質問にお答えします。(全ての質問にお答えできない可能性もございます。何卒ご了承ください。)
●本講座で使用する資料や配信動画は著作物であり、無断での録音・録画・複写・転載・配布・上映・販売などは禁止いたします。
お申し込み方法
★下のセミナー参加申込ボタンより、必要事項をご記入の上お申し込みください。