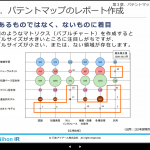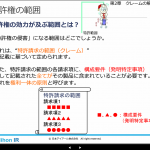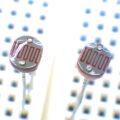情報との付き合い方を考える《技術者とインテリジェンス》

目次
情報は「情(ウエット)と報(ドライ)」が合わさったもの?
一般的に「情報(広義)」といわれている中身には、次のような段階があるといえるでしょう。
まず、生の情報は通常「データ」(data)といわれ、文字、図形、画像、映像、音声などを狭義の情報(information)と呼びます。
その狭義の情報に自分の考え、判断、分析などを盛り込むと、これが「知識」(knowledge)となります。
さらに、その知識にその人の体験や深い洞察などが加わると、それは「知恵」(wisdom)となるのです。
通信から得る情報は「報」で、単なるお知らせである
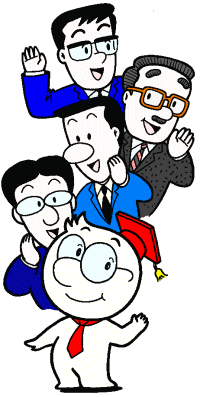 身近な情報源としてインターネット、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌など入手手段は多くあります。
身近な情報源としてインターネット、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌など入手手段は多くあります。
何処にいても均質で新しい情報の入手ができる「デジタル情報」は、ビジネスのヒントにはなるでしょうが、そのまま使える保証はありません。
自分にとって役立つ情報は、やはり「対話」から得られたものが殆どといえます。
対話といっても、具体的に相手がある場合と、自分の頭に引っ掛かっている情報との反復(やり取り)があります。その情報を反復する最中に閃きを生むケースがあるのです。相手との対話は、自分が発する情報に受け手側が、その情報に加算して返してくれば、更に対話が膨らみ新しい情報が生まれます。
同じ体験をしても、ある人の話には含蓄があって、ある人の話は通り一遍で終わってしまいます。それは視点の違いや発想の違いからくるものです。
対話を膨らませる情報活用
ある人が言う。
「今年の夏は暑かった」。
また、ある人が言う。
「アラブの人も40度を越すと駄目らしい。仕事をしなくなるので、天気予報では40度以下にごまかして発表するらしい。日本人は40度を越しても満員電車に乗り込んで、ご出勤に及ぶのではないだろうか」と。
ちょっとした違いですが、話をするなら後者のような話のできる人とお付き合いをしたいものです。
情報に色や匂いをつけられる人は、普段からの習慣が身についていることが多いです。
情報に血を通わせるには、諸々のベクトルが必要
対話をするには、まず相手のことをよく知ることが大事であり、相手とコミュニケーションが成立するには、何か共通のものがあれば話しは弾みます。趣味が同じ、出身地が同じ、同世代である、同窓生である、彼女(彼氏)がいないなど、きっかけは何でもいいのです。
そして情報に血を通わせるには、熱意だとか行動だとか、別のベクトルが必要となってきます。
情報は、元々が「無味、無色、無臭」なのです。
誰かが積極的に関わることで、熱を帯び、色が付き、味が付き、匂いを立て、やがて血が通うものです。
情報の捉え方に個性が出る
新聞・雑誌などで「コラムニスト」といわれる人がコーナーを持っていますが、彼らはいわば”視点の違い”をウリにしている人たちです。
視点が違うからどうしたというのだ、という意見もあるでしょうが、少なくとも対話の材料にはなる利点があります。そういう意見自体が視点の違う意見で、対話がそこから始まります。
情報を自分なりに加工できる能力は、現代に必須なものであるといえるでしょう。
新聞情報は、世間の縮刷版
新聞は、できる限り目を通すことをお勧めします。
なぜなら新聞は、世間の縮刷版みたいなもので、雑多な情報が盛り込まれています。4コマ漫画にも世情が現れています。読者の声も参考になるし、広告欄を丹念に見て、世相を眺めるのもいいでしょう。
このゴッタ煮性が新聞のいいところです。紙面から関心情報を選択する時は、斜め読みし、関心情報は深読みするのです。
旅行先で地方紙を読むこともお勧めです。
全国レベルでは小さな扱いでも、その地方に関わることであれば大きな記事になっています。
例えば、沖縄基地に関する記事、原発の再稼動に関する記事などは地方紙ならではの視点で書かれています。東京から発信する情報量は、膨大だが網羅的で分散している分、現場の声が聞こえにくい面があります。地方紙は東京にいる欠点を補ってくれます。
また、書店の新刊コーナーをウォッチするだけでも流行や社会の動向が見て取れます。
例えば、人間が抱えている不満や不安の解消法、投資に失敗しない方法、高齢者向けの生前整理の仕方など、世相に反映した書籍が並んでいます。

ネットからの情報収集は簡単です。
しかし、自分の見たい情報だけに偏り、そこで思考回路が硬直し「インテリジェンス力」が弱まる危険性があります。
テレビで、ある実験結果を放映していました。
分からないことを調べる時に、ネットから調べたことはすぐに忘れるそうです。
でも、紙の辞書から調べたことは、記憶に残りやすいそうです。
情報との付き合い方を考える
情報の大海で漂流しない!
ネット社会では情報収集には困りません。新しい情報が次から次へと飛び交い、つい2~3週間前の大事件が思い出すことさえできません。
それらの情報に素直に反応しているかぎり、ただの情報スピーカーになり下がります。
自分が発信者側に回ることで、見えないものが見えてくることがあるのです。
情報の大海で、漂流しないためには、情報と付き合う知恵を身につけることが重要です。

情報と上手くつきあう「コツ」とは
- 情報は、マイナス情報に対して敏感になる。
- 情報は、生活情報やビジネス情報のレベルで掴む。
- 情報は、入手するだけでなく自分の言葉で発信してみる。
- 情報は、独自の視点で自分なりに加工する。
- 生きた情報は、人と人の対話から生まれることを忘れない。
- 生きた情報は、現場にある。気になる情報は、絶えずメモをとる。
情報は、誰もが平等に得ることができるのです。
その情報を、どうビジネスに生かすかは、各自の目利きのレベルになってきているのです。
大事なことは、物事を現場の視点から発想することです。
ある人曰く、口は一つしか無いが、目と耳は二つある。
つまり、余計なことは言わずに「倍、聞いて、倍、見なさい」ということのようです。
本当に重要な未来情報は、現場からしか生まれてこないのです。
(次回に続く)
(日本アイアール 知的財産活用研究所 N・Y)