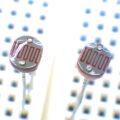【医薬品製剤入門】舌下錠の基礎知識

「舌下錠」は、舌の下に入れて溶かして薬の成分を吸収させる錠剤です。
溶けやすく工夫された剤形で、舌の下の粘膜から直接吸収されるため、速やかに吸収されるのが特徴です。
なかなか舌下で溶かす薬を使用する機会は少ないと思いますが、今回は、舌下錠についてまとめてみました。
目次
1.舌下錠とは?
日本薬局方では、次のように記載されています。
「(1) 舌下錠は,有効成分を舌下で速やかに溶解させ,口腔粘膜から吸収させる口腔用錠剤である.」
舌の下に含んで、溶け出す成分を口の中の粘膜から直接吸収させるようにした錠剤で、作用発現時間が非常に早いという特徴があります。
舌の下の粘膜から直接吸収されるため、体内へ早く吸収されます。直接血中に入り患部に届きます。
薬の成分が胃や肝臓で分解される(初回通過効果)ことがないことから、速やかな効果をもたらします。
狭心症発作時に用いるニトログリセリン錠などは、この特徴を活かしたものといえます。
2.他の口腔内用の錠剤との相違点
- トローチ剤: 口中で薬が徐々に溶解するように硬く加工された大きな錠剤で、口腔内または咽頭などで炎症を鎮めたり殺菌をしたりします。
- バッカル錠: 奥歯と頬の間に入れて、唾液でゆっくりと錠剤を溶解させ、時間をかけて口の中の粘膜から直接吸収させるようにした錠剤です。即効性を期待した剤形ではありません。
- 口腔内速崩壊錠(OD錠)・チュアブル錠: OD錠は口中で水なしで速やかに溶ける錠剤で、チュアブル錠は噛み砕いて服用する剤形です。ともに飲み込むこと(嚥下)を前提としている剤形である点で舌下錠と異なります。
[※関連コラム:チュアブル錠の解説はこちらをご参照ください。]
3.舌下錠のメリット・デメリット
舌下錠は、下記のようなメリットがある製剤です。
- 口腔粘膜から速やかに吸収され、効果発現までの時間が速い
- 初回通過効果を受けることがないことから、高い効果が期待される など
ただし、下記のようなデメリットもあります。
- 飲み込むと、作用の発現が遅れたり、初回通過効果のため無効になったりする など
4.舌下錠の製造方法
舌下錠の製法としては、日本薬局方の口腔用錠剤の欄に下記の記載があります。
「(2) 本剤を製するには,「1.1.錠剤」の製法に準じる.」
舌下錠は、通常の錠剤の製法に準じて製造することができます。
すなわち、錠剤を製造する際に用いられる各種圧縮法が選択可能とされます。
また、湿式錠剤化法によっても製造されることがあります。
5.舌下錠の添加物
舌下錠に用いられる添加剤としては、通常の錠剤に用いられるものと同様な添加物が使用されますが、中でも、D-マンニトール、クロスカルメロース、ゼラチンなどの口腔内速崩壊錠によく用いられている添加物が多く使われています。崩壊性が求められることが理由と考えられます。
例えば、ニトロペン舌下錠の添加物は、乳糖水和物、セルロース、シクロデキストリン、トウモロコシデンプン、ポビドン、ステアリン酸Mgとなっています。
また、アブストラル舌下錠にはD-マンニトール、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、クロスカルメロースナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、三二酸化鉄が用いられています。
6.舌下錠の製剤特性
舌の下側に入れて速やかに薬剤を口の粘膜から吸収させる必要がありますので、剤形としては、急速に崩壊することが求められます。
崩壊時間としては、中には分単位のものもありますが、具体的には下記のようなものが挙げられます。
- シクレスト舌下錠:崩壊試験の結果、10 秒以内に崩壊した。
- ミティキュアダニ舌下錠:崩壊時間 10 秒以内
- ニトロペン舌下錠:崩壊時間 約34 秒
(各医薬品インタビューフォームより)
また、舌下錠としては、小型である方が有利といえます。
舌下に入れやすく、より少ない唾液で溶けるため崩壊時間も早くなります。
7.舌下錠の試験法
日本薬局方では、医薬品として製造された舌下錠が、下記試験法に適合することが定められています。
① 製剤均一性試験法
個々の製剤間での有効成分量の均一性の程度を示すための試験法です。
有効成分の含量が、表示量の一定範囲内にあることを確認し、均一性を保証します。
製剤含量の均一性は、含量均一性試験又は質量偏差試験のいずれかの方法で試験されることになっています。
第十八改正日本薬局方6.02に詳細な試験法が記載されています。
また、舌下錠は、適切な溶出性又は崩壊性を有することが定められています。
② 溶出試験法
経口製剤について溶出試験規格に適合しているかどうかを判定するために、また、著しい生物学的非同等を防ぐことを目的としている試験です。
第十八改正日本薬局方6.10に詳細な試験法が記載されています。
③ 崩壊試験法
舌下錠が試験液中、定められた条件で規定時間内に崩壊するかどうか否かを確認する試験法です。
製造工程のバラツキが小さいことを確認するための品質管理が主目的としています。
第十八改正日本薬局方6.09に詳細な試験法が記載されています。
8.舌下錠の医薬品
添付文書情報で、舌下錠を調べてみると、以下のようになりました。
- 種類 : 舌下錠
- 医薬品数(*): 7
- 主な医薬品 : 「ニトロペン舌下錠」「シクレスト舌下錠」「アブストラル舌下錠」等々
(*)医薬品数はジェネリック医薬品なども含みます。
9.舌下錠に関する特許・文献調査
(1)舌下錠に関する特許検索
J-Platpatを用いて舌下錠の特許を調査してみました。(調査日:2021.4.19)
① キーワードによる検索
- 舌下錠/CL ⇒ 171件
② 特許分類(IPC)による検索
IPCには舌下錠に対応する分類はありませんが、舌下錠に関する特許公報を見てみると、A61K9/20[特別な物理的形態によって特徴づけられた医薬品の製剤 ・丸剤,ひし形剤または錠剤[2]]が多く付与されています。まず、この分類で検索してみます。ただし、A61K9/20は、「丸剤,ひし形剤または錠剤」を対象としているので、キーワード等で絞り込みが必要になります。
- A61K9/20/IP ⇒ 17719件
- A61K9/20/IP*舌下/CL ⇒ 501件
- A61K9/20/IP*舌下/CL*錠/CL ⇒ 389件
これらの中には、「リルゾールの舌下製剤」「舌下用アポモルフィン」「エダラボン・(+)-2-ボルネオールの舌下投与用医薬組成物」「舌下錠剤投与形態物」等々の特許が見受けられました。
③ Fタームによる検索
舌下に関連しそうなFタームとして、4C076BB02[医薬品製剤 適用部位 ・経口 ・・舌下]がありますので、これを用いて検索してみます。
- 4C076BB02/FT ⇒ 978件
これらの中には、「舌下投与用ゼリー剤」「舌下アレルゲン免疫療法におけるフィルム製剤」「全自然非毒性舌下薬剤の送達システム」などもヒットしました。
4C076BB02は「適応部位」に関するコードなので、実際の調査では、調査目的に応じて使い方を検討する必要があります。
(2)舌下錠に関する文文献調査
JSTが運営している文献データベース「J-STAGE」を使って文献調査をしてみました。(調査日:2021.4.19)
- title:(舌下錠 or (舌下 and 製剤)) ⇒ 27件
- abstracttext:(舌下錠 or (舌下 and 製剤)) ⇒ 38件
これらの検索結果の中には、「C-23 ブプレノルフィン舌下錠の品質改良」「ニトログリセリン舌下錠の安定化」「肺水腫におけるニトログリセリン舌下錠の臨床応用」「ブプレノルフィン舌下錠の調製と臨床効果」といったようなタイトルの文献が見られました。
以上、今回は「舌下錠」に関する基礎知識をご説明しました。
(日本アイアール株式会社 特許調査部 S・T)



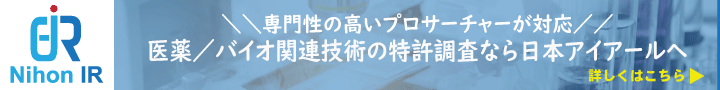





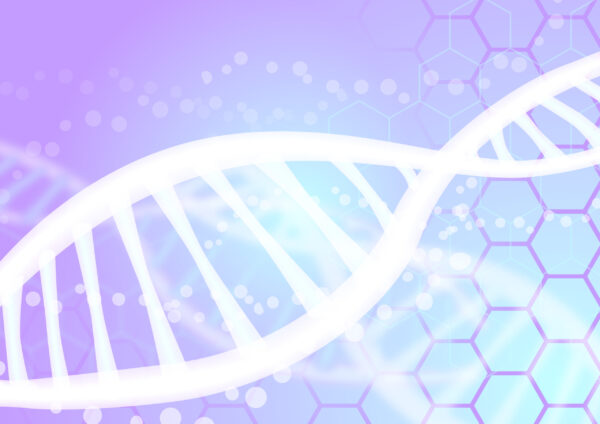
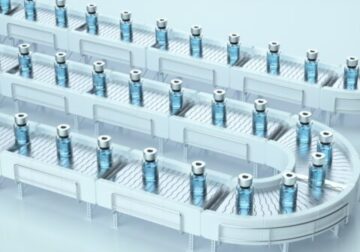


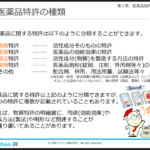
](https://engineer-education.com/wp/wp-content/uploads/2024/01/crushing-150x150.png)