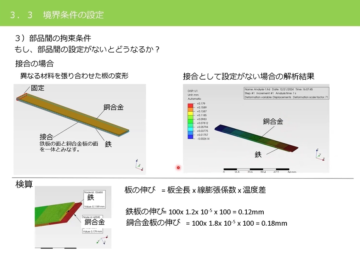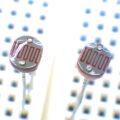演習付でわかりやすい!はじめて学ぶ金属材料の強さと疲労強度(セミナー)
| 開催日時 | 未定 |
|---|---|
| 担当講師 | |
| 開催場所 | 未定 |
| 定員 | - |
| 受講費 | 未定 |
《機械設計者、生産技術者にとって必須》
演習付でわかりやすい!
はじめて学ぶ金属材料の強さと疲労強度
講座概要
「物体がこわれる。」製品にとってこれほど深刻なことはありません。
「なぜ壊れるのか」→「壊れにくくする(強度向上)」→「壊れなくする(保証)」が機械材料には必要です。
材料強度は大きく分けてふたつあります。ひとつが本当の強度(理論強度)、もうひとつは実際の強度。本セミナーでは「実際の材料強度が何によって支配されているのか」をわかりやすく解説します。
受講後には、材料の強さの正体が今までよりも格段に理解できるようになります。
セミナープログラム(予定)
Ⅰ.金属材料の強さについて
(1) 強さの基本・引張試験を正確に理解する
降伏現象(転位の働き)とは
(2)同じ鉄(鋼)でもなぜ強さに差があるのか【演習】
強さに影響を与える因子とは(組織、温度、変形速度、熱処理の影響)
(3)ふたつの破壊の形態
延性破壊と脆性破壊、脆性破壊は統計学的に考える。破壊確率の求め方(ワイブル関数)【演習】
Ⅱ.金属疲労の基本
(1)なぜ金属は疲労するのか。疲労のメカニズム
(2)正しい疲労(S-N)線図の読み方と書き方、疲労強度と疲労限度の使い分け
(3)疲労強度に与える諸因子の影響(材料硬さ、応力比、寸法効果、変動応力、残留応力、微小欠陥がある場合)【演習】
Ⅲ.応力集中とき裂について
(1)ものは必ず応力集中部から疲労破壊する
(2)応力集中係数とは
(3)応力集中部の疲労
(4)応力拡大係数Kと破壊靭性値K1Cを理解しよう【演習】
(5)き裂材の疲労とは。疲労(S-N)線図の読み方
(6)生産に必要な材料硬さとき裂感受性の関係
Ⅳ.質疑応答など
主な受講対象者
- 金属材料を扱って機械設計、生産技術、製造に携わる方。
- 高校数学の「指数/対数の意味」「微分積分の意味」がわかる方。
- 大学の統計、材料力学を履修していなくても理解できます。
期待される効果
- 金属材料の強さの基本的事項を理解できます。
- 「材料強さ」はひとつのものだと感じているかもしれませんが、様々な角度(温度、速度、サイズなど)から材料や製品の強さを検討できるようになります。
- 製品で破壊が発生した時の破壊原因の究明が格段に速くなります。
- 製品設計する際には未然に破壊原因を取り除くことができるようになります。
- 計算式を感覚的に理解し、演習を通して現象をつかむことができるようになります。すなわち、実際の開発、製造現場で使う知識が身につきます。
- 材料強度、金属疲労に対してさらに深い視点が得られます。
公開セミナーの次回開催予定
- 開催日時:未定
- 開催場所:未定
- 受講料 :未定
- 定 員 :オンライン受講は定員無し
※受講時は関数電卓(指数対数の計算をします)とものさしをご準備ください。
※開催1週間前までに最少開催人数に達しない場合は、実施をキャンセルさせていただくことがあります。
※開催の場合は、開催1週間前程度から受講票と請求書を発送させていただきます。
※北條講師による出張セミナーをご検討の方は、お問い合わせください。
お申し込み方法
★下のセミナー参加申込ボタンより、必要事項をご記入の上お申し込みください。